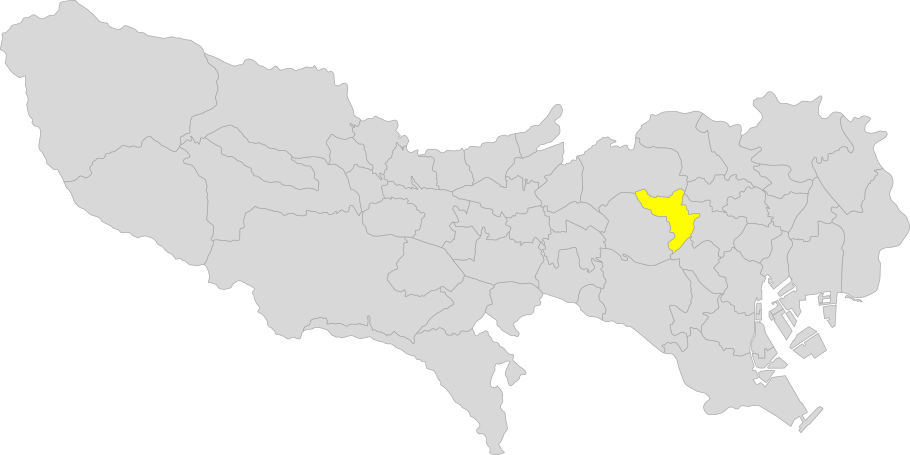(東京都全体については「東京都の概要」参照)
中野区の空爆被害
〇空爆日:昭和19年11/24、12/27、20年1/27、2/16・17、 4/13−14、5/24・25、6/10(全9回)
〇被害状況:死者約430人、負傷者1620人、被災者7万2530人、焼失等家屋2万780戸。
〇出征者と戦死者数:出征者不明。戦死及戦病死者は19年が441名、20年が808名、昭和6年の満州事変から18年までの死者は不明。20年の戦争終盤からの戦死者が多いことがわかる。相対的にみて、19、 20年の戦死者が圧倒的に多い。なお基本的にどこの自治体も(一部の村単位を除けば)出征、戦死者の正確な数はつかんでいない。その理由は敗戦直後にその記録は政府の指令により、全国で焼却されたからである。各役所には兵事係があってそこで出征と戦死者関係はきちんと記録されていたし、特に18年以前はないわけがない。19、 20年の記録は中野区が独自に調べなおしたものと思われる。その焼却というのは占領軍の追求を恐れて、国がその戦争責任を放棄したことを表している。
空爆被害の詳細
17年(1942)4/18:米軍の太平洋上の空母の艦載機(B25)による本土への最初の空爆の日であり、野方町で自軍の対空高射砲弾の破片により一人負傷。荒川、葛飾、新宿区等参照。この後の本格的空襲まで2年半の間がある。
19年(1944)11/1:空襲警報が鳴り、まもなく超大型爆撃機B29が飛来、偵察する中、地上から高射砲が砲撃するが届かず、そのまま去っていった。この年の7月、米軍は日本軍の占領するマリアナ諸島のサイパンやグアム島を陥落させ、そこをB29の基地として整備、日本への空爆体制を整えた。ちなみにB29は日本爆撃用に開発された最新鋭機であり、搭乗員は12名、爆弾や焼夷弾を大量に搭載できた。またB29は高度1万mを飛び、日本の高射砲や戦闘機はそこまで届かなかった。届くのは、B29が爆撃する時、高度を下げてきた場合であった。
11/24:本土への本格的空襲が始まった日で、B29・110機が武蔵野の中島飛行機工場に向かった。区内では鷺宮の家一棟が破壊され、4名圧死、子供一人を救出。
12/3:主に中島飛行機への空襲で、中野区でも消防の出動があったとするが、詳細不明。
12/27:本町と西町、東郷町に投爆され死者2、負傷者12。この日、中島飛行機へ向かうB29を日本の戦闘機約200機が迎撃し、一機が体当たり攻撃をし、B29一機を撃墜、しかし日本機は20機以上が撃墜された。
20年1/9:区への直接被害はなかったが、空中戦により日本機の体当たり攻撃でB29・5機が各地に墜落、搭乗員全員が死亡している。千光前、宮園通、野方町、江古田、沼袋、鷺宮などにそれぞれの残骸が落下した。
20年1/27:本町通に初の焼夷弾が落とされ火災発生。また高射砲弾の破片により朝日ヶ丘で死者1、負傷者2。
2/16:関東全域に艦載機約290機が来襲、区内では機銃掃射により「若干の死傷者を生ず」。
2/17:主に江東区方面への爆撃で、中野区内では負傷者1名。
3/10:いわゆる東京大空襲の日。江東・墨田・台東区の下町地区が焼夷弾による絨毯爆撃を受けて大火災が生じ、この日だけで約8万人千人が焼死し、世界の戦史上最大の犠牲者を出した。三区と東京都参照。中野区の被害はなかったが、逃れてきた被災者を大きな結婚式場日本閣に収容した。しかしこの日本閣も5月の空襲で焼失する。 病院には焼けただれてうめき声をあげている人がトラックで運び込まれた。
4/13−14、東京全区にB29約330機来襲(3/10よりもやや多い)、都内の死傷者約6800人、家屋全焼等約16万8500戸、被災者約71万人、区内では昭和通、桜山、住吉、上高田、大和町、鷺宮などの家々が焼失したが、3/10の大量死の例もあって人々は先に逃げ、死傷者3人と少なく、全焼家屋783戸、被災者3千人超であった。また都立第五高女(現富士高校)と当時中野区にあった昭和高女(昭和女子大)が全焼、近くの寺にも焼夷弾が落ち、その寺の玄関先に逃げ込んでいた親子3人が焼夷弾の直撃を受け黒焦げになって死亡(上記の死傷者3人と記録が異なる)。この日はB29が超低空で爆撃していて、陸軍中野学校にあった高射砲が数機撃ち落としたとあるが墜落場所不明。
5/3−5、5/11:区の記録に空襲との記録はあるが、偵察機の恣意的な空爆のみか。
5/24未明:B29が525機来襲(城南大空襲)、それまでの空襲を通して最大の機数であったが主に港、品川、大田区の被害が甚大、中野区では鷺宮で負傷者3名、家屋の全焼29、被災者124人。住民が高射砲でB29一機を撃ち落としたのを見たというが、世田谷区参照。またこの日の死者は全体で600人に満たず、3/10(301機)の人口密集地帯の被災での大火災の規模がどれだけ悲惨なものであったかがわかる。
5/25−26:夜間よりB29が470機来襲(山の手大空襲)、中野駅から東側、つまり新宿区側がほぼ焼失し、死者418、 負傷者1600以上、全焼家屋2万戸以上、被災者7万人以上の、区として最大の被害を生じた。都内全体の死者は約3600人。この日はやはり風の強い日であった。
この中野区の死者418は身元の判明した者とあり、「防空壕で埋まったりしてはっきりわからない人はもっとあったと思う」とある。別な記述でも防空壕で蒸し焼きにされた人が多いとある。大火災になると火は風を呼んで地上を覆うようになり、簡単な被せ物では持たない。「電柱には沢山焦げた人がぶら下がっていた」とあるが、どのように逃げようとしたのか、しかし煙に巻かれてうつ伏せになって窒息死し綺麗な姿で死んでいる人も少なくなかったとある。
火が収まって昼頃に、防空頭巾をかぶってフラフラ歩いている人もいて、どこへ行くんですかと聞くと、自分でもここがどこかもわからないという人もいた。またいくつも例があるが、この時代は前夜に米を研いで釜に水を浸しておくが、家が焼けても釜だけが残っていて、半炊きになっていればまだ焼け跡に残っている火の上で炊き上げてみんなでおにぎりにして食べたとか、あるいはちょうど程よく炊きあがっていたという話も残っている。
この日の犠牲者約400体以上は4日後に塔山公園に仮埋葬され、翌月合同慰霊祭が行われた。戦後に掘り起こし火葬、改葬された(ちなみに3/10の公園などへの仮埋葬はこの比ではない)。別な話では、身内の遺体を火葬しようにも、落合の火葬場は4/13の空襲で焼けてしまい、堀ノ内は身元のわからない焼死体が山のように積み上げられて、薪もなく遅々として進まず、仕方なく個人の庭先や焼け跡の空き地で焼いたという。
これまで5ヶ月の間に警戒警報と空襲警報が鳴り響いたのはおよそ1200回とある。その度に人々は防空壕との往復を繰り返した。
6/10:『戦災誌』の記録にはないが、打越町(現・中野5丁目)でP51戦闘機の機銃掃射を受けたとある。
焼失した小学校など
米軍は狙いやすい学校をむやみに空爆したが、5/25を主として全焼した区内の小学校は以下である。
全焼:上高田小学校・新井小学校(上高田と新井は統合し現・令和小学校)/桃園小学校/塔山小学校/谷戸小学校/向台小学校/仲町小学校/中野神明小学校/東中野小学校(廃校)/塔ノ山小学校/中野中学校(現明大付属:当時は5年制)/都立高等家政女学校(現鷺宮高校)/東亜工業学校/寺院は他に薬師と百観音、宝仙寺が全焼した。
半焼:啓明小学校/宝仙学園小学校
戦時下の出来事
以下は主に中野区の記録からまとめ直したものである。
戦時下の概要
12年(1937)7月:盧講橋事件により日中戦争勃発。その後、国民精神総動員運動、出征兵士武運長久祈願祭、そして上海戦線の快挙を祝って、大提灯行列が行われ、中野区だけで3万人が参加。
13年:軍需工場動員法、国家総動員法、燈火管制強化、16歳以上の学生の勤労作業促進等実施される。
14年:中野区愛国女子団結成、徴兵検査基準を緩める兵役法改正、国民徴用令(国家総動員法により、戦時下の重要産業の労働力を確保するために、国民を強制的に人員配置できるとした)公布。「青少年に賜わりたる勅語(天皇のお言葉)」が各学校に配布される。
15年:紀元2600年(神話上の神武天皇即位の年を紀元とする)記念祭が各地で展開、同時に物資の配給制が強化され「ぜいたくは敵だ」「ほしがりません、勝つまでは」という合言葉のもと、各種の制限や禁止事項が押し進められ、大政翼賛会、大日本産業報国会発足。劇場やダンスホールも閉鎖、英語なども使用禁止。この年の中野区の人口は214,117人と最大となっていた。米英からの経済制裁が始まる。
16年1月:『戦陣訓』(生きて虜囚の辱めを受けずの言葉が記される)等発布。3月、尋常小学校は国民学校と改変、「皇国の道に則りて」と天皇の臣民である少国民としての教育と鍛練が計られる。8月、中学校以上に学校報国団結成を指示。9月、金属類回収令が公布、施行され、官公署・職場・家庭の区別なく金属類が供出され(寺院の梵鐘まで)、武器生産に向けられた。11月、国民勤労報国協力令公布。これにより14歳以上の生徒の勤労動員が企図された。このような経済的にも非常に苦しい状況下で、同年12/8、日本はハワイの真珠湾に奇襲攻撃、同日にマレーシアなどにも石油を求めて侵攻、太平洋戦争(大東亜戦争)に突入した。 「真珠湾攻撃で成功したという放送を聞いた時は、思わず飛び上がって万歳を叫びましたね。… この調子でいけば絶対うまく行くと確信しました。あんまりその気持ちは長く続かなかったけど」とは一市民の回想である。
17年:味噌醤油の配給制はもとより衣料品も切符制になる。全ての出版物が検閲され承認制となる。海外の戦線は拡大しつつ、ミッドウェー海戦で敗北、日本海軍は主要な戦艦を失った。
18年:女子学生を含めた勤労動員促進、徴兵年齢を引下げ、同時に大学生の徴兵猶予撤廃、学徒出陣として戦地に送る。防空壕建造命令。金属回収令がさらに拡大、家庭の鍋釜・箪笥の取手・店の看板・火箸・花器・仏具・窓格子・時計鎖・指輪・金属ボタンなども回収された。
海軍にいた男性は「海軍は転勤があって、船から陸へ上がって移動してまた船に、そして船から船に、すると今残っている船はどこに何がという情報が読めて、18年6月頃には”もう負けるな”と確信しました」と語っている。
19年:女学校の卒業生や就業していない14−25歳の女性に対して女子挺身隊結成させ、中野区は主に中島飛行機に動員された。また食料増産用に12歳以上の中学生を動員、8月から小学生3−6年生の集団学童疎開開始。11月24日、米軍の本土への本格空襲開始、以降9ヶ月続く。
20年(1945)5月:同盟国のドイツ降伏、一方で日本は翌6月「本土決戦断行」と最高指導会議で決定。しかしすでに3月下旬から3ヶ月の激戦を経て、6/23、20万人の犠牲者を出して沖縄が陥落、事実上の本土決戦の身代わりであった。「最後の方になって、竹槍持ってアメリカ兵が上陸してきたら突くんだといって訓練したりした。ああ、これは終わりだな、勝ってる勝ってるなんて嘘だと思いましたね」とある女性は語っている。
この6月の区の人口は約12万4000人と約4割減となった。地方への疎開者がそれだけいたということである。
7/16:米国で初の原子爆弾実験成功。7/26、連合国が日本に対しポツダム宣言を発し、無条件降伏を要求、しかし日本の軍政府は無視、戦争を継続するとして米国に原爆を使用する名分(きっかけ)を与えた。そして8/6、8/9に広島、長崎に原爆投下。さらに8/8、ソ連(ロシア)が不可侵条約を破棄して日本の占領する満州に侵攻、日本軍だけでなくすでに多くの移住者がいたため、その後多くの悲劇が襲った。8/10に降伏を受け入れ、8/15正午、天皇の詔勅(玉音放送)により終戦となるが、その日の昼まで米軍は空爆を続けた。
当時の世相
昭和に入って日本は深刻な経済不況下にあり、その危機感が軍部を煽り、海外進出に打開策を求めていく要因になった。まずは昭和6年(1931)の満州事変に端を発し、12年(1937)7月、日中戦争突入、12月に南京陥落占領で区内でも祝賀大提灯行列が催されるほどに当時は国民全体が帝国主義思想(当時の日本は大日本帝国と称していた)に染まっていた。
例えば当時中野駅北口の西側一帯にあった陸軍電信隊の近くに住んでいた作家の平林たい子は、「ある晩、電信隊から出征する中年の兵士の列をのぞきに行った。彼らは、わき上がる歓呼の中を無表情で駅から輸送列車に乗った。近くの市民は誰から聞いたともなく寄って来て、叫ぶように”万歳”の声を兵士たちにあびせかけた。… 道の両側に(日の丸の)手旗をもってならんでいる彼らは、ちぎれるほどそれを振っては”万歳”をわめき立てていた。目には狂った光がそい、肉親を見送っているわけでもないのに、わけのわからない涙さえあふれさせていた。… このころから街には日の丸がやたらにはためいて、あらゆる音響物をかき鳴らすような興奮の中に、国中がひたされた。…こういう社会情勢の中に立つと、… (戦争反対の)私たちは、まるで異邦人みたいなもので、… そ知らぬふりで遠まわしに語るよりほか仕方がなかった」と語っている。
当時子供だった女性は「戦争反対なんて夢にも思ってませんでした。言われたことに従うことだけ考えて、(学校でも)そういう風に育てられていたんです。今の子供たちには理解できないでしょうね」と。自由にものが言える時代ではなく、平和という言葉も禁句で(しかし軍政府は東アジアの平和のための戦争としていた)、社会・共産主義はもちろん、自由主義、民主主義的活動も治安維持法によって取り締まられ、場合によっては投獄され、拷問され、死者も出た。この時期、死者が出たとしても 社会的に問題とされることはなかった。
ともあれ「勝って来るぞと勇ましく、なんて一応格好はつけます。そうしないと近所の人にいろんなことを言われるから。でも赤紙(召集令状)が来て嬉しい者がいるはずがない、仕方ないと諦めていただけです。今の若い人は断ればいいじゃないかと言うけど、当時は断ることは死ぬことよりも難しかったんです」。
また元特攻隊長は「教育というものは恐ろしい。ぼくらは陛下のために死ぬという教育です。これをずっと子供の時からやられると、それが当たり前になって、反抗することも意見を言うことも許されない。たとえ上官の命令が間違っていても、従わなければならないのが当時の教育の主体です。戦争というのは全くの人殺しです」と。
当時は全てが天皇の名の下に行われていたが、それが昭和天皇の意思ではなく、周囲を取り囲んでいた軍政府が天皇に自分たちの都合の良い情報しか与えず(国民に対しても同じであったが)、天皇はその意見に従って詔勅なるものを発していた。天皇は本来、国民(当時の明治憲法下では臣民)の生活の安寧を願う立場であり、天皇がそれを自覚していなかったとは、つまり自分のために国民に命を投げ出してくれと考えていたとはとても思えない。 いずれにしろ、「天皇の軍隊」の組織の末端では「上官は天皇の命令と思え」という悪しき思想がはびこり、暴力が蔓延していたが、誰も抵抗はできなかった。
建物疎開
昭和16年(1941)末の新たな「防空法」により都内に防空空地や空き地帯が作られることになった。大事な軍需工場を守るためもあったが、建物密集地帯での延焼を防ぐためもあった。19年に入ってから第一次建物強制疎開が東京都で始まったが、中野区は実際に空襲が始まった後の20年2月から実施することになり、中野駅南側を中心として約1ヶ月かけて、豊多摩刑務所の囚人、徴兵年齢に達しない学生、町会の人々によって約千軒の指定建物の取り壊しを行なった。しかしそれが完了する直前の3/10の大空襲の被害を受けて、さらに空地帯を作ることになり、中央線沿い南北30m、本町通を80m幅で取り壊すことになった。これには軍隊も出動し、牽引車で曳き倒していく荒っぽいものであったが、この工事で家屋の下敷きになって兵士が二人、町会青年部の一人が死亡した。「ほんとにひどい強制疎開でした」とある。この作業は5月まで続き、ちょうど5/25に第六次の建物疎開を終え、旧庁舎前の疎開跡地で完了式と宝仙寺で建物供養を行って一息ついたその日の深夜、大空襲で建物疎開を実施した地域の大半が灰燼に帰した。大きな労力の無駄であったが、逆に撤去させられた人々は引っ越したおかげで多少の家財が守られた。なお、本町通の空地帯は残っていないが、青梅通りがその名残のようである。
学童集団疎開
昭和12年(1937)の日中戦争突入の頃より、特に戦時下教育が徹底され、16年(1941)年春からは小学校は国民学校と改められ、その主旨は「皇国の道に則りて•••• 国民の基礎的錬成を為す」ことを目的とされた。皇国とは天皇の統帥する国ということであるが、「大きくなったらお国のために役に立つ人」になる、つまり戦地に行けば勇敢に戦い、お国(天皇)のために命を捧げるのだという固定観念が昭和の初めから子供の心に刷り込まれていた。教科には国民科、体練科が強化され、上級生には剣道や柔道、女子には薙刀も必須科目となった。
太平洋戦争の戦況が厳しくなると、本土への空襲が予想され、まず学童の縁故疎開が奨励され、19年4/1現在で中野区は1,731名が縁戚のある地に疎開した。しかしそれでは不十分と、政府は集団疎開を決定、対象を小学校3-6年生とし中野区は疎開先を福島県と長野県へと割り当て、同年8月までにそれぞれ4,307名と約3,640名、計7,947名の児童が疎開した。宿泊先は寺院、旅館、錬成所などであった。最初子供たちは遠足気分であったが、数日もしないうちに親元から離れた寂しさが襲いかかった。夜になって一人が泣くと、伝染してみんなが泣いた。次に襲ってきたのが空腹であった。田舎にもまともな食料がなく(軍隊に優先的に供出されていたため)、育ち盛りの子供には足りず、イナゴだけでなく男の子たちは蛇や蛙を採って焼いて食べることも覚えたが、蜂の子を取ろうとして蜂に刺されて死ぬ思いをした子供もいた。時折逃げ出す子もいたが、すぐに連れ戻された。この時期の子供たちが覚えたことは食べ物がないと人間は精神的にダメになることだという。
当初の疎開は翌20年3月までの予定であったが、空襲の激化により継続され、そこに新1、2、3年生も追加された。その3月9日までに6年生は卒業と進学の目的で帰京したが、3/10の大空襲で下町の児童の多くがせっかく会えた親とともに焼死した子もいる。
この3月に帰京した6年生女子は「兄が自転車で迎えにきてくれ、”おかえり”と伯母が私を抱きしめた。その夜から私は病気になった。みんなでささやかなお祝いをしてくれたが、私の胃はほとんど食べ物を受け付けなかった。夢にまで見た家庭のご飯だった。それなのに •••• 消化する力を私の胃は持っていなかった。胃の許容量は極端に小さくなってしまっていた。気の抜けた廃人のように2、3日することもなくおかゆを食べ、物干し台でぼんやり日なたぼっこをした。••• この時私は初めて”敗戦”を感じた。”少国民”の気負いは完全に壊れてしまった」と記している。つまりそれほどに疎開先での食事が乏しかったということだが、まるでナチスに囚われたユダヤ人やシベリアに抑留された日本人の強制収容所の生活を思わせる。同様の話は終戦後に帰ってきた子供たちにも散見される。疎開先によっては多少恵まれた場合もあったようであるが、当時は日本中が食糧難の中にあった。
その後疎開先の福島県と長野県にも空襲があり、一部は再疎開を余儀なくされた。子供たちは疎開先で敗戦のことを聞いた。たまたま出かけていた一人が村役場で聞いて、帰ってみんなに言ったら、お前は非国民だと非難されたという。日本は最後は神風が吹いて必ず勝つという教育しかされていなかったからである。そこからいろんなデマが飛び交い、本土決戦はこれからだと言って竹槍を作ったりしたグループもあるという。そのうちアメリカ兵がジープで田舎にもやってくるようになった。
終戦が決まっても疎開組のほとんどが、すぐに帰れるわけではなかった。焼けた東京の受け入れ体制の問題と、列車の手配の問題で、最終的に10月の下旬から11月にかけて東京に帰ってきた。駅に降り立った彼らが見たのは、廃墟同然になっていた中野の街であった。
空襲下の体験
以下は以下は『東京大空襲戦災誌』第2巻から拾い出したものである。
当時中野区東郷町に住む16歳の阿部悠紀子の話である。
—— 5月25日、当時、私は女学校を四年で繰上げ卒業し、上級学校の入学式が7月に行わなわれるのを待ちつつ、女子挺身隊として働いていた。この日父は防火用水として風呂桶に水をいっぱいにしていて、私はそろそろ床についたとろだった。そこに空襲警報があり、庭の隅に掘った防空壌に家族会員が入った。しだいに空襲の音が近くにやってきたが、焼夷弾はちょうど電車がホームに入ってくるような音をたてて、火花を散らしながら落ちてくる。弟が壕の外に出て「凄い凄い」と見ているので、私も顔を出すと、問もまく照明弾で昼のように明るくなった。空を飛んでくるB29が地上の炎で黒く浮き出て見える。母は台所から鍋釜や私達のお弁当箱やら、夕食の残り御飯を庭の隅の防空壌に入れたりしていた。火はみるみるうちに近づき庭の芝生に火の粉が飛んできて燃えはじめ、父は母に祖母を連れて先に避難をさせた。父と兄と弟、私の4人がまだ火を消すつもりで飛び回っていた。いよいよ家を捨てねばならない時がきた。私はまず湯ぶねに頭からつかった。門の前に立って家の方をふり返ると、熱風が顔に当たりもう隣の家は焼け始めているようだった。四人で走った。……自転車をひいている人、電話機をもっている人、子供をおぶっている人などの姿が瞼に浮かぶ。荻窪町方も、新宿の方も駄目、進退きわまった感じだった 。三重の塔のある塔ノ山公園(今は中学校)に行くと塔も炎に包まれて焼けおちていた。私達は逃げ場に迷った。結局、家からもっと南を流れている神田上水に入ろうということになった。兄と弟は二人で一個のバケツを持ち、父と私はそのあとを走り始めた。が、すぐに猛吹雪のように火の粉が吹き荒れて、身体が風のため横倒しになりそうになる。私は「お父さ ん、戻りましょう」と言ったが、父はうなずいて兄と弟のあとを追って行った。私にはそれ以上体力がなかった。
……塔ノ山公園の隅にかなり大きな地下壕があり、そこに人びとが入っていくのが見えたので私もそれに習った。ロウソクがともり、何十人かの人びとが坐っていた。壕の中では隅にいた私と同じくらいの女の人も身内の人と離れてしまったとのことだった。その脇には、火傷で目が見えないと男の人がねころんでいた。「痛い、痛い」と声をあげながら歩きまわっているお婆さんの両足は火傷で皮がたれ下がっていた。幸いに壕は無事だった。人の話によると、私達が入る前に大勢で入っていた人達は、壕の中は危険だからと全員が出され、指定の場所に避難させられたが、その場所に焼夷弾が落ちたとのことだった。外に出てみると空はやっと白み始めていた。火の手はあちこちに見えたが、殆ど燃えるもりは皆燃えてしまって、方角がわからなかった。私は家に帰るまでに死体があったら(父や弟を確認するため)みんな見ていこうと思った。交差点から50mぐらい入った所で、さっき走ってきた道路の反対側に一人が仰向けに倒れていた。上半身は衣服まですっかり焼けていた。立派な体格の人だと思った。
焼け残ったレンガの門柱が見えた。家影は全く消失し、あの茂った寺院の林も、丸坊主の焼け木に変わっていた。門を入ると兄の姿が見えた。「お兄さん」あとは言葉も出なかった。弟はまだ帰ってとないという。そこへ父が来た。見ると父は顔からリンパ液が流れ、両手はまるで手袋をぶら下げたように、皮がそのままの形でむけて垂れ下っていた。兄も右の手首が一皮むけ、顔も火傷していたが、兄に言われ父を病院(東京女子医専)へ連れて行くことにした。歩いて行くより仕方ない。私は父に念のため、もう一度さっきの死体を見て行とうと言った。今度はバンドのバックルが目に入った。いつも弟がつけていたものだった。さっきはもっと大人にみえたのに。そこへ母が祖母の手をひいてもどってきた。母は火傷した父の姿を見、弟の亡骸を前にして、放心していた。弟を焼跡に運ぶ手筈をきめて、父と病院に向かった。父は病院に着くまでに何度か「可哀そうに、晃を見殺しにしてしまった」と自分を責めていた。幸いに老人が乗っている軍隊の乗用車が一台止まっていた。頼んで同乗させてもらった。電線が各所に垂れ下がり、走るのも大変だった。途中から先に行かれず、そこから幼年学校の石塀に沿って歩いたが、所々に全身の衣服が焼け、うつぶせになっている何体かの死体にあった。
兄も火傷がひどく入院し、母は虚脱状態になり、焼跡に帰って弟の頭を抱いて泣いた。しかし悲しんでばかりはいられず、私は戦災証明書をもらいに行ったり、死亡屈を 出したり、それに焼跡を物色にくる人達に持っていかれないように使えそうな物は確保しておくために、整理もしなければならなかった。検死はざっとすみ、翌日、弟は庭で荼毘に付された。勿論花もお線香もなく、裏のお婆さんがお経をあげてくれただけが手向けだった。骨を納める器もないので、残っていた火消しつぼに納めた。焼け残った自転車で私は病院を往復したが、父は四日後に亡くなった。父も病院の近くの焼跡で野焼きをして、骨は標本アルコール漬け用のガラスびんに収められた。この時はどんなに動いてもお腹は空かず、配給された乾パンものどを通らなかった。肉親を二人も失い 、住む家もなくなったが、まだ家族の遺骨を拾えたのは幸いだった。 中野坂上から成子坂にかけて、350人の命が亡くなったという。その多くの人達は共同の穴の中に入れられ、埋められたのだった。
当時、中野区富士見町の主婦で49歳の白鳥模子(のりこ)の話である。
—— 昭和20年5月25日夜(晴強風)、午前と午後の2回、B29一機が偵察に来て家の上を通過した。折柄主人は勤務先が栃木県の会社なので殆ど疎開同様で、東京にいることは少なかった。夜に入り9時のラジオ放送が始まると、黒猫のクロンベエが帰ってきて、八畳や次の間の六畳を、ガアオンガアオンと火のつくような鳴き方をしてぐるぐる回り、そして私等が床を敷き、私は今のうち一寸でも寝ておこうとモンペのまま、頭巾を枕元に置いて寝ているところにやってきて、いきなり私の頬を爪をかくした手で打った。「何をする」と私が避けると、今度は私の襟首を着物ごとくわえて引っぱる。娘はこれを見て「アラッ、これはもしかすると」と言いかけた時、サイレンの音。この猫は前年11月1日にB29が偵察に来た時から、何かを感じ取り、ラジオより先におよそ一時間位も早くさわぎ出し、東京空襲があるとギャアオギャアオと鳴いて隣家の縁側へとぴ上って知らせたりして、ただ本当の空諜警報が出ても、浜松、名古屋等の他の市にゆく時は知らん顔して、出窓に寝ているで、隣組の人びとは仕度の都合等ある時、お宅の探知器はどうしていますかと聞きに来る。名前もタンチキと変わる。今この探知器がこのさわぎではてっきり今夜はここだという気がする。
「サア編隊だ」と娘は叫んで庭に降り立ち仕度をする。私は重要品を小さくまとめて丈夫な風呂敷に包み腰に固くしばりつけた。ラジオは「南方洋上数目標、北上中、空襲までにはまだ間があるから充分用意して敢闘する様」と言う。やがて空襲警報がうめく様に鳴り出した。ひとまず隣の留守番の娘さんと一緒に家の防空壕に入り、猫も娘の膝の上に乗る。やがて敵機は一機ずつ来て照明弾や焼夷弾を落とし始めた。猫は怒り声を上げて壕を飛び出し、どこへか退散。我々も大変ととび出したが、こう風が強く火の手が早くては、防空必携に書いてある戸を開いて置けなどとんでもない、片っぱしから戸を閉めて戸に水を打ちかける。代々木か戸山の陣地の高射砲は余程腕のいい撃ち手と見え、続いて入ってくるB29を撃ち落とした。我々は拍手喝采した。中には命中して炎を吹き乍ら海町方へ退去するのを止め、急に機首を返して京浜地区の方へ墜ちてゆくのもあり「こんなの日本の真似したな」なぞといっていたが、すぐ隣家に焼夷弾が落ちてきた。(注:この時近くでは大田区の久ヶ原に一機が落下、搭乗員の7人が死亡、4人がパラシュートで生き残り、捕虜となり、「日本の真似をした」一機は川崎市に墜落、9人が死亡、2人が捕虜となっている。その他この日、B29は15機程度が東京地域で撃墜されている。もとよりB29が低空飛行でないと撃墜できないが、3月10日の大空襲の時から比べると、日本軍はかなりの確率でB29を撃墜している。ただしその中には戦闘機による体当たり攻撃も含まれる)
「神谷さんに焼夷弾港下!」と叫び乍ら、庭の池に満々と入れた水をバケツに汲んで庭づたいに駆けつけ打ちかける。みんなの協力でやがて火は水だけで消えた。もう一つの焼夷弾も座敷へ落ちたが、家の人が座ぶとんに包んで外へ捨てて無事。そうこうするうちに、富士見町にも火が回り始め、少し離れた真南の大寺海軍少将のお宅の二階にも火がついた。少将は68歳とかだが昔、江田島で鍛えた体、身軽に庇に乗って巧に焼夷弾を消され、そこに隣組の東大生が駆けつけて、水をどんどん運んで、火は忽ち消し止められた。辺りはどこを向いても火の手で昼の様、煙はのどや眼を刺戟し、鼻水は出る、目はヒリヒリ痛む、火の粉は降る雪の様に竹の垣根に止まり、パッと燃えると、パサッと垣根がたおれる。何処からか二枚折の扉風が飛んで来て池の上に浮かぶ。庭の大松の枝がバサッと落ちる。向こうの広町にある二件の邸宅が仕掛花火の様に美しく燃えていた。
防空群長がとんできて「今夜はもういけませんよ、早く逃げなさい」、警防団員の方も「もう御婦人は逃げて下さい、あとは引き受けます」と言われ、和田見橋の方へ三人でゆくと、すでに都の防空壕は女子供で満員、外も二列に並んだ人々が大勢しゃがんでいる。風が強くて立っていられない。私は少し離れて和田見橋のコンクリートの袂に寄ってしゃがんで休む。この時頭の上を一編隊が過ぎたのが最後であった。しばらくしてどうなったかとうちの方へ行ってみた。ちょうど洋画家の家が焼けている最中で、そのあおりで群長の家から火が出ようとしていた。みんなで池の水を汲み運び続けてなんとか消し止めた。わが隣組7軒は奇跡的に焼け残ったが、焼け出された人たちのことを思えば心なしに喜ぶわけにはいかない。
明るくなってみると庭には油脂焼夷弾が4本、逆さに落ちていた。門から外を見ると先ず、淀橋の瓦斯タンクが無事に見えた。一寸右を見ると淀橋の三越の赤いマークが見え、また少し左の伊勢丹は何という幸運か、明るい色でちゃんと残っている。あんなに何回も淀橋は空襲にあいながら不思議だと思ったら、敵サンの目算があったわ け、後でわかった(注:これは米軍が戦後の占領時に米軍の施設として使える建物を外して空爆していたということである。これは例えば大手町のホテルやビルが残されたのも同様である)。どちらを向いても、田舎まで焼野原、南から西へ目を移すと箱根、足柄の連山、富士山が今迄よりずっと大きく見えた。杉並区との界に流れる神田川のみ昨日と変らず流れている。家に帰り裏に回ってゆくと、丁度クロンベエが帰ってきた。全身泥の中にもぐっていたのか、張子の猫の様、四肢は棒の様、私等を見て一寸口を開いて白い歯を見せたが、人間も猫も、ニャンとも声が出なかった。
わが富士見町は過半数焼け、亡くなった方はなかったと思っていたら、よそで焼け出されてこの地の知り合いに身を寄せていた方が、赤ちゃんを背負ったまま隣家が焼けるのを消火に当たっていた時、焼夷弾が赤ちゃんの首をもぎ取ってしまったという傷ましい事件があったと聞いた(筆者は同様な例を他でも数例読んでいる)。焼け残った家々よりお米を出し合い、罹災者に炊き出しをした。そこに沖縄の敵が全面降伏したとのデマが飛び、首を傾げる人、本気になる人様々だった(ひと月後、沖縄は敵味方20万人の犠牲者を出して陥落した)。
当時中野区城山町に住む主婦で37歳の斉藤ふみの話である。
—— 昭和20年2月、私はその時中野駅近くで、上空からヒラヒラ舞い落ちて来たピラの一枚を拾って驚いた。それは米機からばらまかれた降伏の勧告文だった。それには「日本の皆さん、戦をやめましょう。戦は軍隊がやっているのです、一日も早く戦をやめて平和な暮しに戻りましょう」と書いてあった。私はそのチラシを見て、敵がこの帝都の真ん中に降伏の勧告文をまきちらすなんて、これで戦に勝つことができるのだろうかと考え込んでしまった。ちょうどその時軍服を着た在郷軍人か近づいて来て。手には(集めた)たくさんのビラを持っていた。「拾ったのですか、そのピラを下さい、ほかにも拾った人がいたら届けるように」といって去って行った。私は憂うつな毎日の生活に、この降伏の勧告文を読んだ後は何ともいえない気持ちになり、戦争は負けるかも知れないとはおくびにも出せない。
4月に入り夜ごとの空襲は中野方面をねらっているような気がした。その頃主人は病気のため仙台の大学病院に入院中で、家は長男を頭に二男三女の子をかかえていた。食生活は苦しくなるばかりで、勝つために勝つためにのうたい文句で、甘い物はもちろん主食のお米すら腹いっぽいには食べられない毎日が続き、夜は夜で空襲におびえる有様だった。戦場は戦地だけではなかった。5月25日の夜、今晩はあぶない、そんな予感がしたので、最後の晩餐をしようと、子供達を集めて有りあわせの物で心ばかりの食事をした。私の予感は的中し、ばらばらと焼夷弾が雨のようにおちて来た。消防団の人びとが「火を消せっ」と叫ぶが、消すどころのさわぎではなかった。少しも早くこの子供達を安全な場所に連れ出さなければならない。四歳の子を背負い、次女、三女の手を両手にしっかりにぎり、長男に長女の手をにぎらせて右に左に逃げまどった。火は四方から上がり、町は、一瞬にして阿鼻叫喚の巷となった。子供連は無言でついて来る。みると東中野駅の方の立木に火がつきポッポッとすごい勢いで燃えていた。「青い木はもえないものと思ってたけど、すごい勢いで燃えますね」と誰かがつぶやいていた。「ああ、地獄とはこのような所をいうのだろうか」と思いながら早く夜が明けてくれないかと、待ち遠しく思った。
夜が明けて驚いた。見渡すかぎり焼け野が原。ひとまず焼けたあとの我が家に帰った。何一つなくきれいに焼けていた。少し離れた所に二つの黒い屍があったが、気の立っている人びとは立ちどまりもしない。遠いと思っていた東中野駅がすぐ近くに見え「あら駅が見える」と娘がとんきょうな声を上げた。自分の家ばかりではなく、うらみっこなしに焼けたのだと思うと、家のなくなったこともそれほど悲しくもなかった。近所の人が「こんな焼け野原にはもう敵さんも弾をおとすまい」と笑った。本当だ。かけがえのない一人息子を戦場にとられ戦死の公報に生きる希望をうしなった老夫妻のなげきを身近にきき、家がなくなったことぐらいで悲しんでいられない気持だった。
満蒙開拓青少年義勇軍
昭和15年(1940)6月、「満蒙開拓青少年義勇軍壮行会」が明治神宮外苑競技場で開催された。中野区の年表にはその翌16年2月に、満蒙開拓青少年義勇軍壮行会、3月に「満蒙開拓青少年義勇軍に中野区から11人入隊(野方尋常高小8人、中野高小3人)」とある。尋常高小とは尋常高等小学校、つまり普通の尋常小学校の上に二年制で設けられた学校であり、今の中学校の代わりのようなものであるが義務教育ではなく、正規の中学校(五年制)とは別で、比較的貧しい家庭の子供たちが通い、大半は卒業すると就職し、家庭に余裕ができればここから中学校(女子は高等女学校)三年から編入できた。
昭和6年(1931)の満州事変後の翌年、日本軍(特に関東軍と呼ぶ)は満州国という仮の政府を樹立し、この地を「王道楽土を建設し、五族協和を実現する」(王道とは天皇が統治するという意味、五族とは満州・日本・蒙古・中国・朝鮮の五民族をさす)というスローガンを掲げ、日本人、とりわけ貧しい農民の移住を村ごと促した。そして昭和12年(1937)に改めて日中戦争に突入する年に重要国策の一つとして満蒙開拓青少年義勇軍設立を決定し、満州の未墾の地に青少年を送り出し、将来の農業経営者を育成することを目的とした。義勇軍は二、三ヶ月間茨城県の内原訓練所で基礎的訓練を行ったが、兵士予備軍ともされ、彼らは農業実習とともに軍事教練を受け、軍事的観点から主にソ連国境に近い満州北部が入植先に選ばれた。
2月の壮行会は15歳以上の若者であり、3月は高等小学校卒業生14歳の少年である。彼らの多くは学校の先生から勧誘され、貧しい家の両親も、国が推進する事業ならと送り出した。その総数(14-19歳の少年)は8年間で全国で8万6530名とされ(満蒙開拓移民団としては27万人)、東京都は1995人としている。ところが20年8月15日の終戦直前の8月8日に突然ソ連(ロシア)軍が日ソ不可侵条約を破棄して満州に侵攻、大混乱と惨劇が生じた。軍人たちは先に逃げ、少年たちは戦争が終わったことも知らず、逃げ惑い、頼れる大人もいないまま興安やチチハルといった厳寒の地に放り出された。粗末な難民収容所で寒さと飢え、病気などで命を落とす者も多く、生き残るために現地の農家や商店で働いた。ソ連軍に捕えられ、シベリアの収容所に送られて過酷な労働で死亡した少年たちもいる。あるいはその後中国の軍隊に入隊し10年近く帰国できなかった者もいた。身元不明の骨になって帰ってきた者たちもいて、今は内原の地の慰霊碑に祀られている。彼らもまた、国に放置されたわけである。
豊多摩刑務所(中野刑務所)
ルーツは江戸の「小伝馬町牢屋敷」で、明治時代に市ヶ谷に移転、明治末に中野に移され豊多摩監獄、後に豊多摩刑務所とされた。大正14年(1925)制定の「治安維持法」により政治犯、極右組織、新興宗教、果ては民主主義、自由主義者等、要は社会活動一般に対する取締りがなされ、さらに昭和16年(1941)に法案は強化され、著名人も含めた「思想犯」がこの刑務所に収容され、未決囚のままの拷問死や獄死もあった。収監されていた人々は大杉榮・荒畑寒村・⻲井勝一郎・小林多喜二・中野重治・河上肇・三木清・壺井 譲治といった、文学者・評論家・学者などが標的にされていた。哲学者の三木清の場合、8月の敗戦によって占領軍(GHQ)が思想犯の解放を命じたにもかかわらず、放置されて9月26日に豊多摩刑務所内で獄死した。
昭和20年(1945) 5月25日の大空襲で豊多摩刑務所は全焼(レンガ造りで構造は残った)、囚人は宮城刑務所に送致された。また治安維持法は敗戦後の10月に占領軍GHQの人権指令により廃止された。昭和21年3月にGHQが接収し、10年間米陸軍刑務所として使用され、昭和32年(1932) に接収は解除返還され、中野刑務所となった。その後住民の廃止運動もあり、昭和58年(1983)に閉鎖となった。
4万坪に及ぶ跡地は昭和60年(1985)、区民公園と災害時の避難場所として 「平和の森公園」に姿を変え、また法務省矯正研修所も設置され、その敷地内に刑務所の表門が保存されている。中野水再生センターも併設され、北側には弥生式住居跡が発掘、再現されている。なお平和の森公園に「平和資料展示室」が常設されていたが、平成28年(2016) 4月に区役所内に縮小して移設された。
陸軍中野学校
日中戦争が始まった頃の昭和12年(1937)に陸軍省が「後方勤務要員養成所」の創設を決定、翌年3月に「防諜研究所」を新設。要はスパイ技術養成機関であった。当初、学生は陸軍士官学校、陸軍予備士官学校、陸軍教導学校出身者から選抜されたが、戦争終盤では一般の大学からの卒業生の採用が多くなった。軍人らしい雰囲気を排除するためという。同年7月より教育を開始、当初は九段の愛国婦人会の別棟を当てたが、翌年4月に中野区囲町に移転、7月に第一期生が卒業した。昭和15年(1940) に「陸軍中野学校」と改名するが、陸軍内でも極秘扱いで看板も設置されなかった。当面の任務は満州の関東軍と支那(当時使われた中国の蔑称)派遣軍の特務機関における防諜・諜報であった。例えば中国において現地住民を日本軍に協力させる懐柔工作が行われたが、特に一期生は東南アジアのほか、欧州、中近東、アメリカ、中南米、ソ連(ロシア)のチタへと各地に派遣された。また参謀本部勤務もあった。
中野学校では陸軍一般の教育とは異なり「名誉や地位を求めず、日本の捨石となって朽ち果てること」を信条とし「生きて虜囚の辱めを受け」てもなお生き残り、二重スパイとなって敵を撹乱するなど、任務遂行最優先で教育された。その内容はスパイ活動の他、謀略、宣伝(撹乱するためのプロパガンダ)等があった。一方で現在の川崎市多摩区に登戸研究所があり、諜報活動に必要な兵器資材が開発され、中野学校と登戸研究所は日本陸軍の秘密戦の両輪とされた。卒業生が出発する前には登戸研究所で必要なものを受け取る段取りであった。中でも「杉工作」といって、登戸研究所で作った偽札を中国まで運ぶ役割もあった。平時では犯罪となることを戦時下では国が平気で行ったわけだが、戦闘による殺人も当然犯罪とならなかったし、占領地での住民に対する虐殺も、敗戦後の裁判で摘発されない限り、犯罪とはならなかった。
昭和16年(1941)の太平洋戦争(軍の呼称は大東亜戦争)開戦時には真珠湾攻撃と同時にマレー作戦として英領マレーシアに侵攻する際に学校の教官とともに数名が役割を果たしたという。しかし翌17年のミッドウェー海戦で米軍に敗北し、参謀本部は武力戦を補うための遊撃戦(ゲリラ戦)を展開すべく中野学校ではそのための教育(偵察や後方撹乱)に力を入れ、最前線に卒業生を送るようになった。18年以降には、卒業生が英仏蘭の植民地であるインド、シンガポール、ビルマ、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ニューギニアなどの南方に次々と赴任、潜入して現地人と組み、ゲリラ活動をすることもあった。それ故に日本軍はアジアの国々の解放のために戦ったという意見も少なくないが、確かにそのような活動に意気を感じ挺身した学校出身者もいたが、すでに日本軍の戦況はかなりの劣勢であり、兵站の補給路も次第に断たれ、軍全体で支援できる状態ではなかった。そのほとんどが出身者個人の熱意による支援活動である。事実、敗戦になってもそのまま現地人と独立運動(ゲリラ的活動)に身を投じた中野学校出身者が各地にいた。
この戦争を軍政府は興亜(アジアの興隆)のための正義の戦争としていたが、その是非は別として、18年から19年にかけて、日本軍は次々と太平洋上の島々の占領地を玉砕戦法で失い、とりわけマリアナ諸島のサイパンが19年6月に陥落してからそこを米軍は最新鋭大型爆撃機B29の主力基地として、11月下旬から日本本土へ爆撃を開始した。つまり中野学校の卒業生たちが各地で活躍し始める頃にはすでに日本の敗戦は決まっていたと言っていい。
別途、昭和19年(1944)8月、静岡県二俣町(現在の浜松市天竜区)に遊撃戦要員の養成を目的として二俣分校が設立された。また、20年4月、東京への空襲の激化に伴い中野校は群馬県富岡町に疎開、富岡中学校の施設を利用して講義が行われた。これは迫り来る「本土決戦」のために長野県の松代に大地下壕を作りそこを大本営とする計画で、富岡は松代と関東を結ぶライン上にあって、そこで遊撃戦のための軍人を養成することに狙いがあったという。
中野学校出身者にとって最大の激戦地は沖縄であった。20年(1945)2月中旬から始まった硫黄島の激戦が5週間の激闘をもって終焉を迎える頃、沖縄に米軍が上陸開始した。それを想定して前年に日本軍は沖縄各地に旅団(数千名単位)を送り込み(その途中で歩兵隊約4100名が乗船した富山丸が途中で撃沈され3724名の犠牲者を出した例もある)、それに合わせて9月、学校出身者42名が離島を含めて沖縄に分散配置された。国頭地区に編成された支隊では中野隊は地元の少年を集めて「護郷隊」を組織し、その中心は召集年齢以下の15−17歳の少年たちであり、彼らを使って防衛として戦闘に邪魔と思われる橋や村を破壊・放火させた。これが遊撃隊(ゲリラ部隊)のなすべきことであった。そして米軍が上陸して戦闘になると、子どもたちは自分の身長を上回る銃や陸軍登戸研究所で開発された特殊爆弾を手に、米軍基地の倉庫を爆破し、戦車に向かって身を投げて行き、米兵たちを苦しめた。しかし米軍の圧倒的な物量の前には虚しい抵抗で、足手まといになる仲間を銃殺もした。その子供たちの無惨な最期の姿は、米国の国立公文書館にある資料映像に残されている。まるで21世紀に入って中東地域に勃興した過激派組織ISが子供達を戦闘員として組織し自爆テロをさせた様相とほぼ似ている。第一護郷隊は610人中91人、第二護郷隊は388人中69人が犠牲になったとあるが、他所に第三も見られたりするから全体像はわからない。これとは別に陸軍が中学生(当時は5年制)の14−17歳を学校別にまとめて鉄血勤皇隊なるものを作らせ、ここで約900名の犠牲者を出している。この 同じ年頃の女学生をひめゆり部隊として介護の任務に当たらせながら、最終的に敵に包囲されたとして自決に追い込んだ話は有名である。
その一方で中野の工作員は地元の有力者や学校教員らによる「国士隊」という秘密部隊を組織し、これは住民の中にスパイがいないか密告させるもので、真っ先に米軍に投降し保護されている家族や外国語に堪能な人をリストアップし、順次処刑していったという。手を下したのは日本兵だけでなく、住民も関与していたという信じ難いことが起こっている。さらに波照間の島民は防諜のためとして悪性マラリア地帯に強制移住させられ、1/3の島民500人がマラリアで命を落とした。少なくとも中野学校出身者は沖縄で戦闘以外のこうした悲劇を引き起こす要因を作っている。
この沖縄戦後(20万人以上の犠牲者のうち、約半数が住民である)、残った中野学校出身者は何事もなかったように本土に戻って「本土決戦」のための準備に専念している。仮に本土決戦になっていたら、沖縄と同じように本土の住民と少年は彼らの指揮するゲリラ戦に巻き込まれていたのであろう。
なお中野学校は二俣分校を含めて2131人が卒業し、戦死者は289名、行方不明者は376名という。それだけ潜伏活動が多かったということだろう。ちなみに戦後30年近く経って、潜伏していたフィリピン・ルバング島で発見され、帰還した小野田寛郎もこの出身者である。
戦後、中野学校の敷地は警察大学校などに転用されたが、2008年に千代田区から東京警察病院が移転してきた。さらにその後、四季の森公園、セントラルパークの造成に伴い、明治大学、帝京平成大学、早稲田大学がそれぞれ中野キャンパスとして新設された。
戦後の出来事
人々の様子
敗戦が決まり「悲しくて悲しくて、泣けて泣けて、勝ってる勝ってるなんてばかり言って、どこどこを占領したなんて言って、でもB29が初めて来た時、もうダメだと思いましたけど。あんなにみんな一生懸命やったのにと思うと泣けて仕方がなかったのです」とある女性が語れば、「ああ、やれやれと思いました。毎晩毎晩、小さな子供たちに防空服を着せて、空襲のたびにおぶったり、手を引いたり、逃げ惑ったから、ああ、今晩から楽に寝られると」 。あるいは、「夜になってもサイレンは鳴らないし、これは嘘みたいで、電燈はつけられるし、防空服着ないで寝られるし、•••• 気分がすーとしたのを覚えています」と別の女性は語る。
16歳で愛国少女だった女学生は「その日も私はまだ勝つと信じていたから、終戦の詔勅を聞いた近所のおじさんが来て”来るべき時が来たね”と言ったから、私も父もカンカンに怒って”何ということを言うんだ”と。そのくらい勝つことを信じていたんです」と。同様に「当時女学生で、100%勝つと信じていた。終戦後、本当の世の中の有り様を知らされた時のショック。私たちは何ととんでもない教育を受けたかと、これは忘れられない」と。
主婦だった人は「こらえてこらえて、耐えて耐えて、最後は焼け野原に放り出されて。本当に戦争って空しい。もう二度とあんなこと、夫や子供を戦争にやるものかと思います」と。
男性の場合、「終戦の日は海軍にいて下北半島の山で防空壕を掘っていた。そこへもう戦争は終わったんだよと言われて、何言ってやがんだと、それが本当だとわかったとたんに力が抜けて、防空壕が掘れなくなっちゃった」とか、中島飛行機で臨時工していた人は、「玉音放送を聞いて、ああ負けたんだなと。… 帰りにどのようにして帰ったかわからなかった。力が抜けて、何のために怪我したのか、国のために怪我したのだけど、亡くなった人はもっと気の毒だと思った」と。中学生は、「急に終戦だと言われても信じられなかった。なんで”神風”が吹かないまま終わってしまったのか。いつか必ず神風が吹くと信じていたから、… いつ吹くのか、… これをみんなで信じていたのだから、不思議です」と。
もっと切実だった、本土決戦用の特攻部隊の人がいる ——「終戦になった日の夜、”出撃、準備せよ”という命令が来た。死なないで終戦になったことで、変な気持ちになっていた時で、早速250kgの爆弾二つを積んで、隊員の爪と髪の毛、遺書を戦闘本部へ持って行って全て準備をすませて寝ていたら、夜中に師団から電話が入って”出撃中止”。それで飛ばずじまいでこうして生きている」。
同様な話で、実際に多くの犠牲者を出した例がある。特攻隊には戦闘機だけではなく、潜水艇「回天」とベニヤ板で作られた簡易な特攻艇「震洋」が用意されていたが、高知県香南市夜須町の港に海軍の手結基地があって、約170人の部隊と震洋25隻が配備されていた。終戦の翌日、部隊に「出撃準備」の命令が無線で届き、基地の拡声機が「敵が本土上陸を目的に土佐沖を航行中」と告げた。船首に爆薬200kgを積んだ震洋を、全員で壕から浜に並べて出撃を待った。 午後7時ごろ、一隻から火が出て、「海へ放り込め」と声が聞こえた瞬間、ボン!と爆発音がして周りの艇に次々と引火し、爆発していった。 特攻兵たちの体は砕け、近くの松林から海の中まで肉片が飛び散った。ほとんど18歳前後の若者111名が無駄に死んだ(とはいえ、この戦争では特攻隊員を含めてほとんどが無駄死にであった)。遺骨を届けた上官に、母親と妹は「戦争が終わったのに、どうして」と泣き崩れた。爆発は燃料漏れが原因といわれているが、命令がなぜ出たのか今もわからないという。戦争下にあっては、このようにどんな犠牲者を出しても誰も責任を負わず、単なる事故のように済ましてしまう。
また中野区の証言資料の中では敗戦の日に皇居前で自決した軍人もいると書かれているが、千代田区参照。
復興へ
昭和15年(1940)に21万4117人だった中野区の人口は終戦の8月には疎開で地方に移住した人も多く、9万8180人と半分以下になっていた。家を失った人々は焼け跡から材木やトタン板を拾って来てバラック小屋を建てて雨露をしのいだ。防空壕にちょっと手を加えたり、焼け残った土蔵に住む人もいた。焼け跡の空き地に菜園を作り、焼け残った木材を燃料にして料理をした。 焼け跡に植えた野菜はよく育ったという。
そのうち海外の戦地や満州などの居留地から帰還して来る人たちが増えて食糧不足は一層深刻となった。しかも20年はコメも不作であった。そこで中野区は一時的に「転入抑制緊急措置」をとった。また篤志家が「戦災者救済協力会」を結成し、占領軍の残飯配給を行うなどして命を繋げることができた人もいて、米国からも小麦粉などの救援物資が届けられた。中野駅北口では闇市マーケットができて高値ではあったが賑わった。そこで買えない人は中央線や西武線を使って田舎に買い出しに行った。しかし現金はインフレの影響で使えず、着物などと物々交換であった。その場合、持ち物全て焼かれた人たちはどうしたのであろうか。
小学生だけではないが、学校に弁当を持っていけない子供も多く、22年(1947)1月から米国からのララ物資(Licensed Agencies for Relief in Asia)による援助で週2回ほど給食が実施された。上記戦災の詳細で記すように、多くの学校が焼かれ、残った学校で午前と午後に分けた二部制の授業も行われた。
(以上は主に中野区の記録からまとめ直したものである)
戦争孤児(愛児の家)
戦争の一番の犠牲者と言える戦争孤児の多くは、そのまま街中に放り出された。孤児の多くは空襲で親を亡くしているが、その中には母親を空襲で、父親を戦死で失っている場合もあり、中国や満州からの逃避行による引き揚げ孤児や残留孤児もいて、それはいくらか後のことである。たとえば3月10日の下町大空襲の時(焼死者約10万人)、小学生は集団学童疎開として地方に送られていたが、その時に親を亡くし、そのまま孤児となった子供が多くいる。また6年生は3月の卒業式と進学を控えて多くが3月9日の夜までに列車で帰京したが、親と再会した喜びも束の間、深夜過ぎの大空襲にあい、親と一緒に死んだ子供たちも多くいた。一方で列車が遅れてはるか向こうの東京方面の空が燃え上がっている夜空を見ていた子供の中に、その親が死んで孤児になったケースもある。しかし為政者は戦後の復興に追われ、孤児のためにはほとんど無策で あり、放置された。その結果、彼らは新聞などでも浮浪児というレッテルを貼られて蔑まれつつ、そしてどれだけの孤児が生き延びられずに餓死や病死を含めて悲惨な状況の中で死んでいったか、上野の地下道には帰る家のない孤児たちが溢れ、一日平均二人以上が死んでいったという記録もある。親戚に預けられても戦後の食糧危機が続く中、邪魔者扱いされ、家事労働をさせられ、学校に通わせてもらえない子もいた。そうして孤児たちは想像を超える苦難の道を歩んでいくが、その中で「お母さんと一緒に死にたかった」「家族と一緒に死んでれば幸せだったのに」という思いを引き摺りながら生き続けていく。運よく結婚して家庭が持てても、死ぬまで自分が元孤児であったことを言い出せなかった人が大半であったという。その彼らの痛苦の人生自体が、戦争孤児が「国に捨てられた」現実を表している。国が起こした戦争の犠牲者であったにもかかわらず、世間には孤児というだけで下等民とみなされ差別されてきたゆえである。
(筆者の台東区や墨田区、江東区および「昭和の戦争と東京都の概要」の「戦争孤児」の項参照)
そうした孤児たちの一部を救ったのは一握りの善意ある人たちであっ た。もちろん善意だけでできることではないが、中野区の一主婦で、比較的裕福であった石綿貞代(さたよ)もそうであった。石綿は戦前から大日本航空婦人会など婦人団体に所属し、傷痍軍人の慰問などの慈善活動をしていた。
1945年、終戦の翌9月、石綿貞代は、知り合いが一人の男の子を連れてきて、面倒を見られないかという話だった。当時家にいた石綿の三女で、やはり疎開先から3月に小学校の卒業式のために帰ってきていた石綿裕が「服に『岡本勝』(仮名)と書いてあって、おそらく小学1年生くらい。ただ、名札以外何もわからない。本人に聞いても、口数が少なく、記憶も曖昧。母はすぐ引き取ることにした。それが最初の子でした」と語っている。しかし「彼は年長の姉2人と寝ることになったが、全身シラミだらけで、大騒ぎとなった。髪の毛をはじめ、洋服の縫い目などにべったりと張りついているシラミをみんなで取っていった」。それでも「学校に入らなくちゃいけないので籍を作って、小学校1年生くらいかな?ということで1年生に入れた」。
そこから貞代は孤児たちの救済をと、その後上野にも出かけ、裕もたくさん握り飯を持って時折ついて行った。上野の地下道には排泄物と残飯に混じって、ボロボロの服を身につけたやせた孤児たちがたくさんいて、焼け残った毛布や新聞紙にくるまって生活していた。男女の区別もつかないくらい垢で真っ黒になった子供が空き缶を持って「頂戴、頂戴」と物乞いをしていた。母がお握りを渡して「うちに来る?」と聞くと「うん」と。それで電車に乗せて連れてくるが、汚いから乗客がサーッと離れていった。家に着くとまず風呂に入れて、ご飯を出す。食糧難の時代だったが、貞代はどこからか米や野菜を調達してきていた。人を安心させるのは温かいご飯が一番、というのが口癖だった。一人一人と孤児たちを連れて帰り、翌21年2月には15人になり、年末には60人ほどになった。自分の3人の子供にも手伝わせ、1947年には多い時は107名になった。売れる着物や道具は売り尽くし、それでも到底足りず、近隣や知り合いにも応援を頼んだ。向かいに開業していた耳鼻科の先生が夕方に来て無料で治療をしてくれ、薬をくれたこともあった。時には家財やお金を孤児に持ち逃げされることもあったが、貞代は愛情をもって育てた。。新たに戸籍をつくった子は4、5人はいた。
ある時には家の前に毛布でくるまれた赤ちゃんが置かれていた。明らかに占領米軍とのハーフの子であった。石綿は数ヶ月育てながら悩んだ末、アメリカ人の里親を探すことにした。日本にいると混血児として差別され、いじめられるのがわかっていたからで、幸いに養子を探しているアメリカ人夫妻に巡り合った。そして約40年後にその子の知人を通じて問い合わせがあったという。育ての親から聞いていてのことであろうが、このあたりはアメリカ人はオープンで、アジア人を養子を迎える例は多いが、日本人には躊躇がある。アメリカでは黒人などに対する明らかな人種差別があるが、その違いはなんであろうか。
貞代にとってやりくりが大変な日々が続いたが、1946年初夏、GHQ民間情報教育局の中尉が愛児の家を視察に訪れた。さらに8月、米軍の星条旗新聞の日系2世の記者が取材に訪れ、貞代の活動を報じた。すると秋には英ロンドン・タイムズの女性記者らが取材に訪れ、愛児の家のことを報じた。次第に米国本土や駐留する進駐軍から援助物資が送られるようになった。クリスマスにはYWCAの人が来て一人一人にプレゼントを送ってくれた。孤児たちは天国にいるようだと思った。米国から日本への援助物資では、1946年11月に始まったララ物資が知られるが、愛児の家にはその最初の物資が送られた。支援の輪は徐々に広がり、1952年に社会福祉法人となり、翌年CCF(基督教児童福祉会)は”愛児の家”をキリストの精神と何ら変わるところがないという見解で、やはり米国から送られた援助金を”愛児の家”に寄附するようになった。CCFの援助はその後貧しい国に移った。「愛児の家」は現在も児童養護施設として、親の虐待やネグレクト(育児放棄)にあった子供たちを受け入れている。 貞代は1989年に92歳で死去、娘の裕が引き継いで幼児の担当として一緒に寝るという生活をしている。
(以上はジャーナリスト森健の記事、その他の記事から混成している)
愛児の家はこうした米国の援助があって幸運であったと言えるが、こうした援助を受けられないもっと私的な施設もあった。またこの愛児の家は1948年の児童福祉法の施行以降、養護施設と認可され、戦争孤児以外の子供たちも収容する体制になり、公的援助も受けられるようになったが、わずかな金額であったという。いずれにしろあくまで孤児を救済するために国が積極的に施設を作った結果ではないことは知っておく必要がある。国は民間人のこうした地道な努力に対し、後追いしているだけの話である。
そもそもこの孤児たちは、国が起こした戦争の犠牲者であったにもかかわらず、空襲による被害者、障害者も含めて、補償として一円の支給も受けていないことも我々は知っておくべきである。もとより戦時下には空襲被害などに対する補償制度はできていたが、3月10日の大空襲以降、政府はその対応を放棄してしまった。それに対し戦争に関わった軍人や軍属の人々は、現今に至るまで手厚い恩給や年金を支給され続けていて、それは子や孫にまで及んでいる。このような対応は先進国の中では日本だけで、同じ敗戦国ドイツは、差別なく補償をしている。仮にも戦後の早くから補償制度ができていたら、孤児たちは親戚縁者にも除け者にされず多少は大事にされたであろうに、これは国家による大きな過失と言っていい。