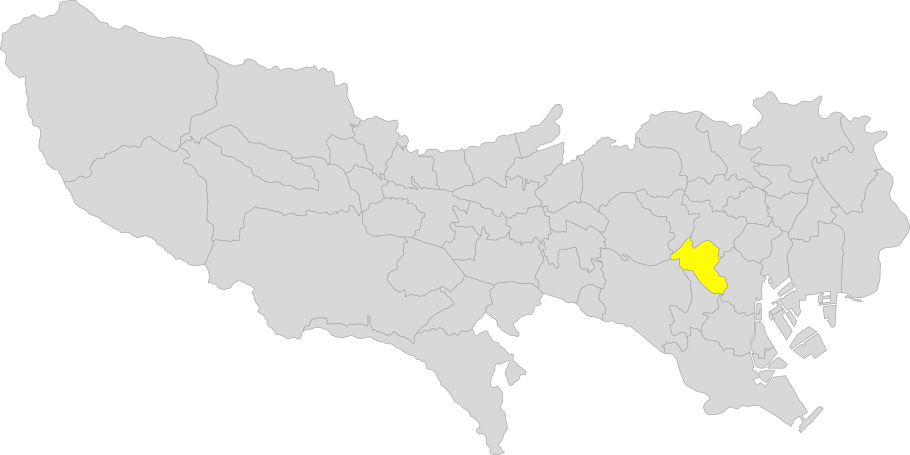(東京都全体については「東京都の概要」参照)
渋谷区の空爆被害
〇空爆日:昭和17年4/18、19年11/27、20年1/27、2/16・19・25、3/10・31、 4/13-14・15-16・19、5/24・25・29、7/28、8/15(全17回)
〇被害状況:死者1140、負傷者5680、被災者21万2120人、焼失等家屋5万6700戸
〇出征者と戦死者数:不明
空爆被害の詳細
17年4/18は米軍による日本本土への初空爆であり、前年12/8の日本軍の真珠湾奇襲攻撃からほぼ4ヶ月後である。太平洋上の空母からのB25中型爆撃機16機を東京から神戸までに出撃させた。渋谷区では第一商業学校の生徒が機銃掃射によって大腿部貫通の重傷を負った。また自軍の対空高射砲の破片によっても一人重傷を負っている。(荒川区参照)
本格的な空爆は二年半後の19年11/24から始まる。その間米軍は、南太平洋上の日本軍占領の島々を制圧することに専心し、そして陥落させた順に島を日本攻撃用の基地とし、そこから新たに開発された長距離大型爆撃機B29(乗員12名)を連日投入して行った。そして日本各地を焼き尽くした焼夷弾も、米軍が日本の木造家屋向けに研究開発したものであった。
19年11/27:B29・62機が来襲、区内は主に原宿地区が被害を受け、死者9、負傷者12、被災者117人。
20年1/27午後:B29約60数機が都区内全域に空爆し、死者約540、重軽傷者約910で、有楽町近辺が機銃掃射を受け100名以上が死亡、駅周辺に死傷者が折重なった。渋谷区は空襲被害はなかったが、自軍高射砲の不発弾の落下によって3名が死亡した。この例は各地であり、2/16も同様で死者なし。
2/19午後:B29約100機による高々度からの爆撃で、都内に66名の死傷者があったが、渋谷区は死者6、負傷者2。千駄ヶ谷で比較的低空で攻撃して来たB29一機を撃墜し機は分解飛散し、それにより民家16戸が全半焼、死者7、負傷者4の被害が出た。米軍機は9名が死亡、2名はパラシュートで降下し、捕虜となった。
2/25:B29約200機が東京の北東部全域に来襲したが、渋谷区は大きな被害なし。
3/10:世に流布する東京大空襲の日であるが、渋谷区は被害はなく、むしろその地から避難して来た人が1000人以上いた。この日の実態は墨田、江東、台東区等を参照。
4/13−14:東京の多くの区部に対し、B29約330機が深夜に来襲、多大な被害を生じた。渋谷に大きな被害はなかったが、明治神宮が集中的に焼夷弾が投下され、御社殿のほとんどが焼失した。城北大空襲と呼ぶ。ただし渋谷区の死者はなし。
4/15−16:B29約110機で、被害は1/3程度、渋谷は自軍機の墜落で円山町の民家25戸が焼失。
5/24未明:これまで空爆被害の少なかった都区南西部に連続して大量の空爆がなされ、品川、大田、目黒区の被害が大きく、渋谷区の死者20、重傷者240、しかし焼夷弾による被害は大きく、全焼家屋約8,860戸、被災者約3万1560人。高射砲によりB29一機を撃墜、爆発して原宿や穏田(現・神宮前)に落ち、乗員10名死亡、うち4名が不明、2名がパラシュートで降下し捕虜となって東京憲兵隊へ送られ、戦後米国へ帰還。少年一人がこの米軍機の下敷きになって死亡。
5/25夜:この日の被害が最大となった。渋谷区の死者約900、重軽傷者約3860人、全焼家屋約2万8620戸、被災者約11万6380である。他に新宿、中野、港、文京区の被害が大きく、この日を山の手大空襲と呼ぶ。この両日で渋谷区内の約77%が焼き尽くされ、小学校17校、中学校3校が焼失した。陸軍刑務所の米軍捕虜62名も焼死(下記参照)。
25日の様子:「翌日、軍の車で戦災状況を視察に行った。表参道のケヤキは焼けただれ、青山方面は瓦礫の焼け野原。表参道と青山通りの交差点横にあった安田銀行の前には、逃げ遅れた人たちが重なり合って倒れ、 黒焦げの焼死体が積み上がり、異臭を放っていた。今でも残っている神宮の大燈籠の台座には人間の油がしみついている」。また幡ヶ谷から初台にかけての平坦な住宅地は、庭に各自で防空壕を掘っていたが、多くの人は自宅が燃え落ちる火勢の中で逃げ切れず焼死した。
実は空爆の規模で言えば、この両日ともに3/10の規模よりも2倍前後大きい。米軍の記録ではB29は5/24が525機、焼夷弾の投下量は3687t、5/25は470機、投下量3302tであり、3/10は約300機、投下量1783tで、それぞれの半量前後である。つまり3/10は乾いた北風が吹き荒れ、それが密集度の高い木造住宅の下町に凄まじい効力をもたらしたわけである。
7/28:P51戦闘機による機銃掃射で渋谷にも多少の被害があった。この二日前の26日に連合国は日本に対し降伏を促すポツダム宣言を発したが、日本の軍政府は無視、戦争継続を発表、その後8/6と8/9に広島と長崎に原爆が投下された。実は米軍は7/16に原爆の開発を終えたばかりで、結果的に米国の狙い通りとなった。
8/15:正午に天皇による終戦の詔勅が発せられる前、代々木練兵場にP51戦闘機による機銃掃射があった。これは『東京大空襲戦災誌』にはないが、実際に練兵場の斜面の防空壕で一時生活していた人(関東高女生)の証言である。すでにB29爆撃機の出動はなかったが、P51戦闘機による遊び感覚の攻撃であり(実際に8/10に日本はポツダム宣言受諾の意向を連合国に通達している)これは正午直前まで各地で行われている。事実、この時は洗濯して広げた白いシーツが狙われたようで、また終盤は外で遊ぶ子供たちもしばしば狙われている。
焼失した小学校など
臨川/加計塚/代々木山谷/笹塚/笹塚/西原/本町/富谷/中幡/千駄ヶ谷/鳩森/神宮前/青山学院/渋谷・大向・大和田(三校は神南小学校へ統合)/(原宿(廃校)/仰徳(廃校)/代々木高等小学校(廃校)
他に、都立第十五中学校(現・青山高等学校)/実践女学校中等部など。
戦時下の出来事
昭和10年(1935)の渋谷区の人口は23万4850人、15年は25万6706人、19年2月は23万9499人となっている。19年は特に男性が93%に減少している。これは軍事工場への徴用や兵役によるものである。そして空襲の激化による疎開などで20年6月には推定人口は4万6538人と激減していた。
空襲下の様相
以下は『東京大空襲戦災誌』第2巻の証言集からの抜書きと要約である。
当時渋谷区千駄ヶ谷三丁目の工場の寮に住み、23歳だった阿部かね子の手記。
—— 工員であった私は、玉川線新町駅前の藤倉工業で働いていた。私と小学校の同窓の宮沢さんは、昭和15年の暮れに故郷の長野から上京して、季節工として勤めたのだが、翌年には徴用にかかり、そのままこの工場の気球部で勤め続けていた。工員の大部分は徴用工で、これは戦争で商売上がったりになった魚屋や、豆腐屋の小僧さん、板前さん達が多く、もう一種類の新徴用工というのは、漁業関係出身の人達で、ほかには動員された学徒なども混じり、出身も年齢もまちまちな人びとの集団だった。宮沢さんの妹も洋裁店を開いていたが、この工場に徴用された。
工場は第一から第三工場まであり、全部で2千人人余りが早朝、工場前に整列して産業体操のあと「御民われら生けるしるしあり…」と報国の誓いをしてから、持ち場につくのが日課だった。時には五人乗りの上陸用のボートなども作らされた。班長の私の下には15、6人の女性達がいた。B29が、最初に工場の上空に現われたのは19年の晩夏だった。あれは何かの偵察に来たのだろうと皆で言いあった。3月10日の空襲は私達の工場には被害はなかったが、同僚の金近さんという男の人は、工場の夜警をするために宿直した9日の晩、洲崎町にあった留守宅は全焼、奥さんと一歳半の坊やが行方不明になってしまった。それから一週間もさがし回った果てに、洲崎の海辺に二人の死体があがった。奥さんは背中に手さげ金庫と、赤ちゃんをしっかりとくくりつけていて、二人の口の中は炭のかたまりがいっぱい入っていたという。金近さんは形見となった手さげ金庫を持ってきて、潮に濡れたお札をひろげて干しながら、その上にポタポタと涙を落とした。工場を守るために、家も妻子も失ったのに、軍からも会社からも一銭の見舞金も出さないのを私達はかげで気の毒がった。
5月の初め、はるかな上空で空中戦があり、小さ在日本機が健気にもB29の巨体に体当たりし、日本機はすぐにキリモミ状となって木の葉のように落ちてゆき、B29は、頭、胴、尾翼と三つに空中分解して落下していった。落ちたのは、千駄ヶ谷の東郷神社の近くときいて、私達は会社の帰りに見にいった。B29の頭部の操縦席には、子供のような可愛い顔をした若いアメリカ兵が操縦梓を握ったまま死んでおり、少し離れたところに落下傘に覆われて若いアメリカの女の兵隊が死んでいた 。見物人は皆、びっくりしていた。(注:この日付のあたりでB29が墜落したという記録はPOWの資料の中にはない。ただし、5月24日未明の空襲で、千駄ヶ谷の鳩森八幡神社の裏手にもB29の機翼が落下したとの証言もあり、この日はPOWにもあり、証言者の記憶違いであろう)
連日の空襲を受けて、工場は群馬県の沼田に移転することに決まり、一ヵ月も前から全員引越しの梱包に忙しかった。やっと製品や機械などの荷造り完了、明日の朝貨車で新宿駅から発送という前夜の、5月25日夜、荷物もろとも、私達の工場は焼かれた。私達にとって不運極まりない夜だった。(以下、空襲時の切迫した様子は省略。阿部も同僚も必死の逃走で助かっている)その後会社から10日間の休暇が出て、各自の郷里へもどった。帰ったきり、戻って来ない工員もずいぶんあったが、ふたたび出社した私達は、やがて工場の移転先の、群馬県沼田へ疎開した。戦後宮沢さんと二人、ふたたび上京してもう二十余年、暮しに追われてついに結婚もせず、働き続けたが、ふたたび人殺しの道具だけは作るまいと、誓いあって生きて来た。
当時渋谷区千駄ヶ谷四丁目に住み16歳の小出渓子の手記
—— 焼ける二ヵ月前、3月10日の空襲の直後、道路を広げるために、わが家は強制疎開の命をうけ、それからは慌しい生活であった。取りこわしの日、大きな家は戦車で引き倒すといわれていた。その日、戦車は来なかったが、土方人夫が大勢で来て、三方から、まず家中の柱という柱を全部根から切り、一大轟音とともに押し潰した。私はそれを見ていてたまらなかった。父はその時どこにいたのだろうか。私達一家は、地続きの家作を空けてもらい、そこに移り住んだ。
それから二ヵ月後の前日、5月24日の明け方に空襲があり、神宮外苑を境にして新宿寄りが焼けたので、わが家は焼け残ったと安心したぼかりだった。25日は早めに床についた。もちろんモンペの上下を着たまま、枕許には鉄カプトほか七ツ道具を全部揃えて寝た。まもなくラジオが機の近づくのを告げた。「今度はやられるかも知れないな」と町会の防空長だった父はつぶやくように言うと、すぐゲートルを巻き直して飛び出していった。その後空襲のサイレンが鳴り、すぐに聞き馴れたあのキーンという金属音が聞こえてきた。母は空襲警報が鳴るたびに、姉二人に手伝わせて、家の中のふとんやなべ、やかん、あらゆるものをボンボンと防空壕に投げ込む。私は弟と防空壕に入った。「敵機来襲、待避待避」と方々で叫び合う声が聞こえる。壕から首を出して空を見ると、幾条もの探照燈に照らされて、あの憎らしいB29の形が明治神宮の森の上にくっきりと照らし出され、手にとるように見える。今日はパカにたくさんだ。…… どのくらい時間が経っただろうか。蓋を少しあけて外を見ていた父が叫んだ。「すぐみんな逃げろ!」私は外をのぞいて驚いた。夜か昼か、自分の目を疑った。空が全体にいきなり仕掛花火をいっせいに打ち上げたような真昼の明るさだった。避難先は明治神宮裏参道(現・北参道)と決められていた(明治神宮の本殿は、四月の空襲で焼け落ちていた ) 。まず私と弟は、背負えるだけの身の回り品を背負い、隣組の老人子供と一緒に裏参道ロータリーへ出た。南から吹きつける強い風に火の粉がまじり、神宮に至るまで渦のような黒い煙であった。まっすぐ立って歩けず、身をかがめ飛んでくる火の粉を消し合いながら、裏参道に集まった。私達は山手線の土手に駆け上がり、千駄ヶ谷の町の焼け落ちるのを眺めた。わが家の近辺は一番最後に炎上した。たった数時間のうちに千駄ヶ谷一帯は、ただ起伏を残した広い広い平野に変わった。わが家は金属も、硝子もみんな溶けてあとかたもなく、母達が夢中になって投げ入れた防空壕の中のものだけが残された。幼い頃みんなと遊んだ鳩森八幡神社の、その宮司一家は、身を捨てて神社を守ろうとして、一家全滅した。
5月26日のひる過ぎ、姉妹三人は焼跡に父母と弟を残し、助かった荷物をそれぞれ背負い、久ヶ原の母の親類を頼って行くことにし、焼跡を出発した。電車は全部不適だった。環状線(今の明治通り)を原宿、渋谷、恵比寿と、見渡す限りの焼け野原の中を三人は無言で歩いた。同じ戦災者の列が群れをなして、延々とどこまでも続いていた。日暮れる頃やっと久ヶ原に辿りつき、その夜から私は40度の熱を出し三日間うなされた。私の身体の回復を待って、母、私、弟は、母の生家である富山県にゆくことに決まった。これからは本土決戦になるから、生きて会えないかも知れない。私達六人は親子、夫婦、別れの水杯を交し、貨車にのって上野を発ち、東京、越中と別れた。疎開して約二ヵ月半で終戦の放送を聞いた。10月半ば、私達一家は焼跡の瓦礫の町へ帰って来た。父のすべての体力と智恵と堪え得る限りの忍耐力で、六畳一間のバラックが焼跡に完成した。回りは焼けトタン、屋根も焼けトタン、容赦ない秋風がトタン板を鳴らして吹き込むと、大きな野ねずみが遠慮なく寝ている私達の顔といわずお腹といわず走り回った。寝ながら月が見え、代々木駅辺りの焼け残りの家の灯がゆらめき、どこまでも続く荒涼たる焼け野原にも、白くコスモスがゆれていた。父は25年秋、わが身をすり減らすようにして、やっと建てた本建築の家の完成を待っていたかのように、53歳でこの世から逝った。
当時渋谷区原宿一丁目に住み36歳の南部きみの手記。
—— 20年5月、幼稚園へかよっている娘が一人いて、東京で二人暮しだった。夫はもとは尾久にある旭電化に勤めていたが、とうとう栃木県の軽金属の工場へ徴用になって、夫婦で離れて暮らしていた。25日の朝、私は疎開するという神宮前にある姉の家へ泊まりにいった。姉の主人も仕事で上海へ行っていた。姉の家は、青山の電車通りから並木道もある表参道を右へ入ったところにあった 。夜になって姉と話が終わって寝ようとすると、警戒警報が出て、そのうちにすぐ空襲警報になった。すぐにB29が、焼夷弾を雨のように投下すると辺りは、真昼のようになった。私は幼い娘を細引で私の身体にしばりつけて、表参道へ飛びだした。表参道の右手の原宿方面はものすごい火の海で、とても逃げられそうもない。表参道を左へ行き、青山一丁目の方へ走った。すると数頭の馬が猛烈な勢いで走ってきて何人かの人が馬に蹴られて倒れて死んでしまった。とっさに青山墓地へ行こうと思った。墓地にたどりつくと近くが燃えはじめたので、墓地の中へ中へと逃げこんだ。墓地の中で娘と抱きあって朝になるのを待った。やっと火勢も弱まり帰途に着いた。電車通りにはロウ人形のような死体がころがっていた。参道の真ん中に老婆が明治神宮の方を遥拝した形で死んでいた。防空壕の中の人はみんな死んでいた。参道に入るかどにある平出歯科の家の人たちは防空壕で一家全滅していた。壕の入口から赤い靴下をはいた三歳の幼女の足だけがみえた。同潤会アパートの前にきれいなお嬢さんが一人死んでいた。衣装も焼けていないし、やけどもまったくしていない。美女が眠ったように倒れていた。おそらく煙にまかれて窒息して死んだのだろう。
姉の家のあった焼跡へたどりつくと、姉も生きていた。よく生きていたとばかり二人で抱きあった。姉の友人が麻布の龍土町にいるというので、そこを訪ねることにして、原宿の方から回っていく時、同潤会アパートの近くで兵隊が死体をシャベルでトラックにのせていた。いったいどこへもってゆくのだろうか。シャベルにのせられた死体は、トラックの上にいるゴムの手袋とゴムの前かけをした兵隊の手に渡され、その兵隊は荷物のように死体を投げていた。「こんなことがあってよいのだろうか」と思い、戦争というものに疑問を感じた。
姉の友人の家でおかゆを御馳走になり、一泊してから次の日、浅草まで歩き東武線で夫の栃木県の職場へ行った。そこはほんとうに狐や狸のでるような田舎だった。その後一ヵ月間ぐらいは兵隊の死体を処理するあの恐ろしい光景が頭にしみこんで、神経衰弱になってしまった。東京にもどってからの生活もさんざんだった。25年に夫は小学校の先生に就職した。夫は京大を出ていたが、徴用のときに毒ガスでやられたのが原因で結核になり、身体検査でパスせず、そのため一生代用教員で終わった。私は電線工場で働いた。娘も結婚したが、幼年時代に寒天とおかゆばかり食べたので、いまでもゼリーとおかゆが好きである。
当時渋谷区原宿二丁目に住む45歳の与世山俊三の手記。
—— 私は兵器産業関係の工場を持ち、景気がよく夜を日についで生産に励んでいた。原宿の自宅も広い敷地で環境も良く、少しくらいの空襲にあっても大丈夫だろうと、たかを括っていた。それが手ひどいショックを受けたのは、3月10目、本所緑町の工場が被災、焼失し、従業員約90名のうち14人が一夜にて行方不明となり、妻の妹も子供3人とともに江東橋付近で焼死したからである。10日以後、私は連日自宅から小半日歩き続け、焦土のあちこちを亡くなった人びとの遺体をさがしに没頭した。二週間を経ても、江東橋付近の川面には、満潮時になると岸すれすれの水の面に数知れぬ水死人が浮かびただよって流木とともに同じところをゆききしている。ふくれ上がってもとの面影をとめぬ無惨なそれらの人びとの遺体を、手かぎで引き寄せては、もしや知り人の一人でもいないかと顔を改めた。焼け残った両国の警察をたずねて、顔見知りの警官から名簿を見せて貰うとやっと一人、庭野という夫婦の名を見出した。死臭に満ちた焦土の中では、持参した弁当ものどを通らず、私は毎日、トボトポと徒労の足を引きずっては家へ帰った。四月半ば近くの妙円寺の住職に頼んで、彼らの冥福を祈ったのが、精一杯の心やりだった。……
疎開していた妻子は、空襲下の私の身の上を案じ、死なぼ家族諸共と決意し、15歳の長女をかしらに4人の子供を引きつれて帰って来たのは、5月24日の午後だった。当惑と喜びで妻子らをむかえて間もなく、翌25日の夜、 怪烏のようなB29が非常に低い高度で飛来してきた。地上からはいっせいに探照燈が放射され、光の中に捕えられた一機は高射砲の弾丸のえじきとなって見る間に撃墜された。その後編隊は高度を上げて次に来襲した、雨のように石油をまき、息つくひまもなく焼夷弾を投下し始めた。3月10日の惨禍の跡をつぶさに見てきた私は、荷物よりもまず人命をと、とっさに決意して「俺は年寄りだからこの家とともに死ぬ」と言っていた老父をいち早く安全念場所へ逃がすことにした。……
明け方、ようやくにして火勢は衰え、敵機も去ったので、妻子とともに表参道を歩いて、我が家の跡へ行とうとした。いずれ身一つで逃げた際に人びとが捨てていったものだろう、食糧や位牌まで、そこらに落ち散っている。表参道を歩き始めた。舗道のアスファルトは燃えとろけて、その上に大人とも子供ともつかぬ黒焦げの死体が、二つ、三つ、とかたまっては枯れ木のようにころがっていた。男女の区別すらもない、まったくの炭のかたまりだった。昨夜、穏原橋の上で表参道へゆけといわれて逃げた人びとだったのかとも思った。幅20mの広い道路も、結局は両側から吹き煽る火勢には役立たなかったのであろう。さらに進むと、参道の尽きようとする手前の右に当たる大きな建物の石塀の陰に、およそ50人位の人が折り重なって死体となっていた。石塀は人びとの姿を熱と流れ出した人間の脂で染めつけていた。ここの焼けこげた木々はほどなく枯れたが、人びとの死の影を染めつけた石塀だけは長く残っていた。
妻子をつれて我が家へ帰りつくと、一物も残さず地上のものは焼失していた。防空壕の中の品々も、簡単なふただけであったために殆ど駄目だった。ただ一人家族に離れて青山墓地に逃げた老父も、微傷だに負わず、元気に帰って来た。防空壕の中の陶器の花器につめておいた米と味噌は無事だったので、破裂した水道管の水で米をとぎ、焼跡の家庭菜園に残っていた細い大根を抜いてみそ汁の実にして、家族の無事を喜び合いながら朝食をとった。皆ふしぎに意気軒昂で、ジメジメしていなかったのはまわりのすべてが焼けていたため、あきらめの連帯感のためであったろうか。代々木にあった私の事務所でも、金子明子という若い事務員が焼死した。それもたくさんの死体の中で江戸紫の小菊の模様のモンペの切れはしが見出されて、やっと身元が確認されたのだった。郷里へ便りを欠かさぬやさしい娘さんだったのに。我が子のように心傷んでならなかった。
学童集団疎開
南洋戦線の敗退から本土への激しい空襲が予想され、昭和18年、都市部の児童には縁故疎開が奨励された。渋谷では19年4月1日現在3254名の児童が縁故疎開していた。その後集団疎開が推し進められ、19年8−9月にかけて17校の3−6年生1869名が熱海などの静岡県へ、5校394名が富山県へ疎開。予定は翌年3月までであったが空襲は激しくなる一方で、6年生のみが卒業と進学のために3月9日までに帰京した。そこに3月10日の大空襲があり、残っている児童の1年生以上から第二次集団疎開が行われ、22校2622名が富山県へと向った。しかし静岡県にも空襲の危険が出てきたため、6月になって1723名が青森県へと再疎開した。
原宿小学校の疎開先は静岡県袋井市で、お寺に分宿した。一人の女子生徒は19年12月7日、農業の時間で三列になってみんなと歩いていた。ちょうど二階建ての家に差しかかった時に、突然大きな地震がおきて上下に揺れたと思うと目の前が真っ暗になって気を失った。気が付いて「助けて」と何度も叫び、背中に家の柱が乗っているのを消防団の人たちがのこぎりで切って助けてくれ、そのまま意識を失って一週間ぐらい寝込んでいた。気が付いたら父がいて、治ったら一緒に帰ろうと言ってくれた。友達は?と聞くと、7人で手を繋いで歩いていた他の子はみんな家の下敷きになって亡くなったという。疎開に出かける日に東京駅に親たちが見送りに来てくれていて、その中で親に泣きついていた友達も一緒に亡くなった。その上、その家族は5月25日の山の手大空襲で逃げた表参道で全員亡くなったという。この方の背中の傷は一生残った。(『昭和の戦争記録』岩波書店より)この時の地震は昭和東南海地震といい、死者は近隣県も合わせて1000人以上であり、住宅の全半壊は5万戸を超えているが、戦時下の報道管制により、新聞などでは報道されなかった。それよりも翌日の12月8日は太平洋戦争の開戦記念日で、戦局が悪化している中、国民を鼓舞する報道の方が大事であったという。
静岡県から青森県へ再疎開した学童たちの専用列車は6月5日に出発、途中で品川駅に寄った。束の間の再会を求めてホームに黒山のように父母たちが待っていた。我が子に渡したなけなしの食べ物・衣類、小さな包みが車内に投げ込まれた。列車は7日正午前に弘前駅に到着。駅前の旅館に数日間宿泊したあと、11ヶ所の寺院に分散した。青森県では、静岡県と比べて食糧事情が悪く子供達は食べ物に不自由した。寺の周囲にいた蛙がほとんどいなくなったのは、食用にされたからであった。終戦の近づく頃、青森市内が爆撃を受け、空が真っ赤に染まっているのが見えた。8月15日の終戦の日、神国日本はいざというときは神風が吹き、絶対に負けないと教育されていた私たち学童には、日本が負けたことが信じられなかった。10月22日の午後、青森県下から帰京。富谷小では校舎が無残に焼け落ちていたが校庭で解散式が行われた。
常盤松開拓団
昭和6年(1931)の満州事変を契機として、疲弊していた日本の農民を満州に移民させる計画がまずあり、満蒙(満州と蒙古)開拓団が日本各地で結成され、日中戦争開戦前の昭和11年(1936)には満洲農業移民百万戸移住計画が決定され、移民は本格化した。ただこの対象は農民だけではなく、特に太平洋戦争開戦以降の戦時体制により、店や工場を失った商工業者もその対象となり、都内でも業者や町単位で集団移住する場合もあった(品川区参照)。
満蒙開拓団についてはその悲劇がさまざまな形で語られてきているが、この常盤松開拓団のことはほとんど知られていない。20年(1945)に入り米軍の爆撃で東京は廃墟となったが、焼け出されて家や職を失った人々が開拓団に応募するようになった。東京農業大学はこの時期、前年から満州に「報国農場」を開拓しており、この年、三次にわたって順次学生を派遣していた。一次隊は4月初旬で、その二次は6月初旬、三次は6月下旬であったが、その間に4/13の城北大空襲、5/24・25の城南大空襲・山の手大空襲があり、多くの都民が焼け出され、東京農大の校舎も焼失した。そこで都が被災者の開拓団希望者を集めて東京農大の学生派遣団に預けた。その二次隊に預けた都民は20人、三次隊に預けた都民は約30人であった。その開拓団の名前は農大の立地する常盤松とされ、合わせて50名の開拓団は家族と単身者で構成され、家族には当然女子子供もいた。行き先は当然農大の満州農場で、その場所は東安省(現・黒竜江省東部)密山県湖北で、ソ連(ロシア)との国境近くにあった。
ところが三次隊は、敦賀からの出航を待つ間、空襲にあい舞鶴に変更。舞鶴では船が機雷に触れて座礁、敦賀に戻って8月3日に出航となり、朝鮮の元山に上陸して列車で満州の牡丹江に着いて市内の宿に入ったのは8月9日午前一時であった。そこから農場に近い東安駅には列車で半日の距離である。このとき空襲警報が鳴り、それは米軍ではなくソ連軍によるものであった。 6日には広島へ原爆が投下され、その虚をついて8日にソ連が日ソ不可侵条約を破棄して宣戦布告、翌未明、つまり三次隊が牡丹江に着いたころにソ連軍が満州に侵攻を開始した。その同じ9日の11時に長崎にも原爆が投下された。そして8月15日に敗戦となるが、連絡網を絶たれた満州の居留民にはその事実が知らされることはなく、とにかくソ連軍と、満州地元民の反乱から逃げるしかなかった。
こうして農大の三次隊は農場にも行けないまま、そこから常盤松開拓団30名も一緒に逃避行となったが、集団で逃避できる状況になく、すぐにバラバラとなった。もとよりこの開拓団にはリーダーがいず寄せ集めの集団であった。ソ連軍の侵攻により、すでに二次隊に付き添って農場に落ち着いていた20名も、農場が虎林市楊崗の開拓民連絡所に先行避難させたという。しかしこの逃避行は交通機関も寸断されて使えず、数10kmから100km単位の行程をソ連軍を警戒しながら徒歩で右往左往している間にソ連軍に捕捉され、その多くが主に牡丹江の海林収容所に入れられた。しかしソ連軍は多数の収容者を扱いかね、難民を9月下旬から収容所から解放、つまり追い出した。
この北の満州の地は10月から急速に寒くなり、真冬は零下20−30度になる。その時期に難民たちは日本に向けて徒歩でさまようことになる。日本の敗戦は9月に入り知ったものが多く、満州を守っていたはずの関東軍はソ連軍の侵攻とともにその多くが四散し先に逃げ、開拓団を守ったという話は稀でしかない。しかも肝心の日本政府が何の救助の手も打たず、開拓団27万人を放置した。その過程で集団自決や足手まといになる小さな子供を殺したり、中国人に預けたりした話は数多くある(中国残留孤児)。避難民は途中で収容所などを転々としつつ故国日本を目指したが、その多くが帰国できずに無念な思いのなか死亡した。終戦後の政府は連合国の占領軍への対応に追われていたとはいえ、あえて言うなら、8月15日の敗戦から10日も絶たないうちに、その駐留軍用に慰安所を作り上げた(大田区参照)。それを終戦二日後の17日に決めたのである。何という早わざであろうか。
もちろん放置されたのは満州の開拓団だけではなく、日本軍が占領した中国や海外の各地に残された居留民そして兵士たちであった。そして満州の難民たちに差し向けた引揚船の第一陣が葫蘆島に到着したのが21年(1946)5月7日であるというからいかにも遅い。この間に何万人の開拓団が死んだのであろうか。もちろん太平洋戦争で大半の船舶が撃沈され、船は決定的に不足していたであろうし、満州ばかりでなく、東南アジア各地にも引揚船を出さなければならなかった事情はあるだろう。終戦後のそれまでに餓死・病死で多くの命がむざむざ失われたし、引揚船に辿り着けないまま死亡した人も多くいる。
この昭和20年に満州に派遣された東京農大の学生たちは16−17歳の新入学生が中心であった。そして教職員を含めた90人以上のうち56人がほぼ翌年の2月までに収容所か逃避行の中で死亡した。そして50人の常盤松開拓団の中で生還できたものは数人に過ぎないという。農大の場合、残りの生還者たちが後々記録を残したりしたので、その受難の経緯はほぼ明らかになっているが、常盤松開拓団の場合、厚生省の開拓団消息簿には不明とあるように、その数人の生存者も確かではなく、その中で当時子供だった輿石大仁郎がただ一人の証言者として現れた。
以下は筆者のサポートスタッフが、2019年に開かれた中国帰国者支援・交流センター主催による拡大模擬発表会(本人ではなく語り部による)で聞き書きしたものと、一部『農学と戦争』(岩波書店、2019年)その他から織り交ぜて概略的に記したものである。
輿石大仁郎は台東区生まれで父親は革職人、母と姉一人と妹一人の四人家族であった。昭和19年(1944)11月下旬より米軍の空襲が激しくなり、一家で山梨県へ疎開。しかし疎開先で輿石が病気になったため、翌年3月初め、一家で東京の台東区へ戻ってきた。そのとき彼は7歳であった。そこで3月10日の東京大空襲で焼け出された。その後親戚の家を点々としたが、生計もたたないため、一家で満州開拓団に参加することになった。 それが東京農大に随行した常盤松開拓団であり(5月とあるが農大の二次隊と思われる)、参加者には農業経験者はいなかった。着任地は農大の湖北農場である。
8月9日、ソ連軍が参戦し隣接する満州侵攻、置き去りにされた開拓団民は襲撃の対象となった。逃げる途中で休んだ食堂のようなところで、3人の兵士が持っていた銃を奪われ、何人かが撃たれた。その騒ぎを見に行った父親も目の前で撃たれて死亡。そのときに見た真っ赤な血は輿石の頭にこびりついている。さらに棒やクワを持った中国人たちもやってきた。母が「逃げて!」と言って……それが母の最後の言葉であり、姉と妹ともそのまま生き別れとなった。輿石は必至で走ったが、追い詰められて溝に隠れるも見つけられ、さらに殴られた。一時気を失ったが、再び意識をとりもどし、一人の青年と出会い、一緒に逃げることになる。しかし大きな川に遮られ、まだ小さかった輿石は青年についていくことができず、そこでまた一人になった。その後、海林収容所に入れられるが、そこで東京農大拓殖科の青年大谷春男(当時16歳)と出会う。大谷は足に怪我を負い、歩くのも難儀な様子であったが互いに助け合って過ごした。
しかしある時、輿石大仁郎は食糧をもらいに行った先で、中国人に別の収容所に連れていかれてしまう。その収容所では中国人が労働力として日本の子どもを引き取ったり、また売買したりしていた(当時の中国の農民は過酷な労働に子供の手助けも必要としていた)。大仁郎はいくつかの中国人家庭に引き回された。そして5番目に引きとったのが現在の養母であり、そこで中国人として大切に育てられた。養母は輿石を護るため、日本人であることを隠し、「張吉凱」の名前で日本語は絶対に話してはいけないといわれた。その後、新疆で学生生活を送り、技術者になって無線第2工場に就職、1964年末に中国人と結婚。 中国人として生きてきた輿石は、すでに中国残留孤児の帰国運動が始まっていて、職場の同僚に残留孤児仲間を紹介され、そこから日本への帰国を考えるようになる。
輿石は養母の前で、忘れないようにつぶやいてきた日本語を口にしたという。「ゴハン、ミソシル、タクアン」。そして自分の本名「コシイシダイジロウ」。感謝の思いとともに「ずっと帰りたかった」と打ち明けると、養母は「わかった」と受け入れてくれた。1983年、輿石は一時帰国することになり、その訪日リストが新聞に掲載された。——「輿石大仁郎 46歳 牡丹江」。それを見た農大の生還者の一人が上記の大谷に連絡を取った。大谷は同じ収容所で、ある日いなくなったその大仁郎であること確信した。12月、二人は38年ぶりに再会を果たした。
輿石は1985年に家族一家4人で永住した。47歳で40年ぶりであった。養母はその4年後に中国で亡くなった。彼は、帰国したらひょっとして、中国ではぐれた家族(母、姉、妹)が日本に無事帰っていて会えるのではないか、という期待をしていたが、残念ながらかなわなかった。帰国後、彼は日本語ができないというハンディを背負って昼夜働いた。中国人の妻は技術をもっていたが、日本語ができないという理由で仕事が見つからず苦労は続いた。
輿石は日本に定住後、請われて自分の体験の証言もするようになったが、インタビューに応じても、つらい記憶がよみがえり、眠れない日が続いた。養母の話をする時も、感極まり涙がとまらなかった。そうしたこと以外は輿石は妻と平穏に暮らしている。なお輿石は家族も含め、常盤松開拓団に参加した他のメンバーに日本で出会うことはなかったようである。
常盤松開拓団が随行した東京農業大学の実態については、「東京都の大学・女学校」の中の同校参照。
海軍特年兵の碑
渋谷区神宮前の東郷神社にこの碑(殉国碑)がある。海軍特年兵とは海軍特別年少兵の略語で、太平洋戦争突入後の翌昭和17年9月、海軍は将来の中堅幹部候補を養成するためとして、高等小学校(注:小学校の上の任意の二年制の学校で中学校とは別)卒業程度の14歳から16歳までの少年を特に対象とした特別年少兵 (特年兵)を募集した。これはいわゆる徴兵ではなく(注:徴兵年齢は順次下げられ、20年には18歳からとなっていた)訓練生としての募集で、当時の少年には海軍は憧れの的で、学校の先生に勧められて応募したケースもあり、親に内緒で応募した場合もあった。当初は一年半の教育と訓練(水兵、機関、整備、工作、看護、主計の各科)の予定が戦況の悪化によって一年に短縮されたりしたが、その結果、15−17歳の少年たちが戦艦などの出動とともに乗組員として乗艦し、あるいは硫黄島や沖縄などの第一線の決戦場に投入され、その多くが戦死した。しかしこれは正式な兵の資格で戦死したわけではない。零戦などによる19歳以上の特攻隊のことはよく語られるが、なぜかこの海軍特別年少兵のことが語られることは少ない。
戦後25年も経って、この生存者たちが全国から寄付を募って碑を建造し、昭和46年5月16日、高松宮同妃殿下の臨席のもと除幕式が行われた。その碑文である。
海軍特年兵
あゝ十四才 大日本帝国海軍史上 最年少の勇士である …… 太平洋戦争の時局下に 純真無垢の児童らが一途な愛国心に燃えて祖国の急に馳せ参じた その数は十七年の一期生三千二百名をはじめ 二期生四千名 三、四期生各五千名 終戦の二十年まで約一万七千二百名におよんだ 横須賀・呉・佐世保・舞鶴の四鎮守府に配属されて活躍した 戦場での健気な勇戦奮闘ぶりは 昭和の白虎隊と評価された (そして)五千余名が 南溟に或は北辺の海に短い生命を散らした しかし特年兵の存在は戦後 歴史から忘れられていた …… このままでは幼くして散った還らぬ友が余りにも可哀想であり その救国の赤誠と犠牲的精神は 日本国民の心に永遠に留め 讃えねばならない ……
吾々は 今は還らぬ幼い戦友の霊を慰め 永遠に安らぎ鎮まらむことを願うと共に 特年兵を顕彰し その真心と功績を後世に伝え 祖国繁栄世界平和を祈願しながら尽力することをこゝに誓う
昭和四十六年五月十六日 海軍特年兵生存者一同
(毎年四月上旬にここで「特年会」の慰霊祭が催されている)
特年兵一期生の体験
元特年兵で第一期生の西崎信夫(2019年時点で92歳:東京都西東京市在住)が『「雪風」に乗った少年』(藤原書店、2019年)という本を上梓している。本のタイトルの「雪風」とは、太平洋戦争末期に敵の攻撃を受けて沈没した戦艦「大和」の護衛にあたった駆逐艦の名前である。以下は西崎が取材に応じて語った内容である。(NHKのサイト「戦跡—薄れる記憶—」より)
西崎は母親のサワの猛反対を押し切って「海軍特別年少兵」に応募し、昭和16年に一期生として合格した。11歳のときに父親が亡くなり、苦労していた母を少しでも楽にさせたいという思いからであった。15歳で広島県の大竹海兵団に入団し、自宅を出発する日の朝、母親にかけられた言葉は、「死んだら何もならない。必ず生きて帰ってこい」だった。見送りの人たちでいっぱいの駅で「バンザイ!」の声が響くなか、汽車が動き出したとき、線路脇の電柱の陰に母親が一人で立っているのに気付いた。日の丸の小さな旗を持って何かを訴えるような母親を見て「絶対に生きて帰ってくる」と固く誓った。
海兵団では厳しい訓練が続き、理不尽な体罰も当たり前のように行われていた。ある日、団長から「戦場における軍人の精神の神髄はなにか」と質問されたとき、母の言葉を思い浮かべ、「生きて帰ることであります」と答えると、「なぜ天皇陛下のために死ぬことだと答えないのか」とひどく叱られ、唯一の楽しみだった夕食抜きの罰を受けた。戦局の悪化に伴い、少年兵たちも次々に最前線に送り込まれた。
昭和20年3月に沖縄に上陸したアメリカ軍の進撃を阻止しようと、4月6日、戦艦「大和」を中心とした10隻の艦隊が沖縄に向かった。そして西崎が乗る駆逐艦「雪風」に「水上特攻」が命じられた(注:もとよりこの時期の戦艦大和は、どこも連合軍による海上封鎖が敷かれていて、すでに活躍の場がなく、大和自体が特攻艦として命じられての出動であった)。「雪風」も食料や燃料は片道分しか積まず、「弾丸を撃ち尽くしたあとは玉砕する」と告げられていた。「出撃する直前、父の形見の腕時計の音がやけに大きく聞こえた。カチカチという音が、自分の命を削っていくように聞こえてならなかった。周りの仲間は遺書を書いていたが、私は母の言葉を思い出して、絶対に書かなかった」。
翌日、鹿児島県沖でアメリカ軍の約200機の大編隊が襲ってきた。頭上で鳴り響くキーンという金属音と弾丸の破裂音。
すぐ前にいた上官が「ウッ」とうなって倒れた次の瞬間、左足の太ももに、焼け火箸3本がブスッと刺さったような痛みに襲われた。痛みにあえぎながら看護兵に「銃弾の破片を抜いてくれ」と頼んだが、答えは「重傷者がたくさんいるから、自分で抜け!」だった。覚悟を決めて戦闘帽を強くかんで息を止め、ピンセットで銃弾をつかみ、渾身の力で引き抜いた。あまりの激痛に全身の力が抜け、残りの銃弾を引き抜く気力はもうなくなっていた。太ももを包帯で縛って何とか戻ると、機銃台の射手として敵機を撃墜するよう命じられた。「このままでは殺される」と恐怖で足が震えるなか、自分自身を奮い立たせ銃を撃ったそのとき「突然、私は開き直った。恐怖が殺意にかわり、弾を撃つことに快感さえ覚えるようになった。……恐怖が殺意にかわった瞬間の感覚がずっと体の中に残っていた」。
いまも脳裏から離れないのは、沈没した「大和」の乗組員の救助にあたっていたときのこと。火薬と重油の臭いが立ちこめるなか、周辺の海では助けを求める乗組員たちの声が響いていた。西崎が甲板からロープにつかまった若い兵士を引き上げようとしたとき、その兵士の足に太った下士官がつかまっていた。「二人一度に上げろ!」と言われても重くて上げられない。「はなせ!」と言ってもその下士官は手を離さない。西崎はその腕を何度も棒でたたいて振り落とし、若い兵士だけを助けた。流されていった下士官がその後どうなったのかはわからない。(注:こうした例は他の証言にもある)
「あの下士官にも生きて帰ってくることを待ち望んでいた家族がいたに違いない。本当に悪いことをした。一日たりとも忘れたことはない。…… なぜ少年たちがこんなに亡くならなければならなかったのか。偉い大人の人たちが始めたむちゃくちゃな戦争に巻き込まれたという怒りがいまも消えない」。西崎によると同じ「海軍特別年少兵」の一期生は約3200人いたが、約2000人が戦死したという。
終戦後の昭和22年10月、西崎は5年ぶりにふるさとに帰った。「ただいま帰ってまいりました」と玄関先で声をあげると母親はまるで幽霊を見るように「信夫か?」と尋ねた。そして目にいっぱい涙をためながら「よう生きて帰った…」といとおしそうに体をさすって迎えてくれた。左太ももにはまだ銃弾が残っている。
筆者注:上記にある沖縄における地上戦でもやはり15歳頃の少年遊撃隊が作られ、爆弾を持って戦車に突撃させるという酷い話が残っている。また、沖縄戦の直前の硫黄島の戦いでは、約2万1千人の守備隊の中に海軍部隊が約7千3百余人がいて、この海軍部隊に海軍特別年少兵3千8百人が含まれていたという。そしてそのほとんどが米軍との激戦の末、玉砕した。実はこうした10代の若年層を戦場に送るのは国際規約違反である。そうした事実を恐れて、日本軍は敗戦と決まってすぐに内外の戦時関連の記録・資料は焼却したが、この特別年少兵の記録も全部燃やされたという。
東京陸軍刑務所焼死事件
宇田川町に東京陸軍刑務所があった。ここでは昭和11年(1936)に2・26事件でクーデターを企てた青年将校らが処刑されたこともあった。米軍は昭和19年11月下旬より超大型爆撃機B29による本格的な空襲を東京地区から開始したが、その時に日本側に撃墜されるか故障などで落下傘で降下して助かった米軍兵士は、そのまま逮捕、拘束され、この陸軍刑務所に収容された搭乗員が62名いた。またここには日本人囚人約400名も収容されていた。本来捕虜は別の収容所で拘束管理されるが(大森区参照)、B29の搭乗員たちは、別扱いであったのか、取りあえずこの刑務所に収容されていた。ちなみにB29の搭乗員は通常11−12名で、墜落した場合、全員が落下傘で助かる例は少ない。
そして5月25日夜間の山の手大空襲の時、この刑務所にも焼夷弾が多数投下され全焼したが、日本人の約400名は解放救出され、米兵士62名は解放されず鍵がかけられたまま監房で焼死した。この時逃れ出ようとした数名の米兵捕虜が看守により斬殺される事件が起きたとされる。逆に看守は牢の扉を開いて、米兵のうち23名を出したが、塀に阻まれていたため逃げ場を失って焼死したともされ、真相は不明とされている。なお、米軍は事前に自軍兵士が捕虜となっている場所を特定し、そこに空爆することはしないが、この渋谷の刑務所の場合、把握できていなかったと思われる。また空襲で犠牲となった連合国軍兵士の捕虜は全国で179人とされる(POW研究会)。
しかし戦後の23年3月から7月にかけて行われた連合軍GHQによる横浜軍事法廷におけるBC級戦犯裁判の結果(戦犯裁判については豊島区参照)、刑務所長のT陸軍大尉が死刑(再審で懲役40年)、看守長のK陸軍少尉が死刑(再審で懲役30年)、米兵を斬殺したとされる看守のOとK法曹長、K軍曹も死刑(ともに再審で懲役10年)の判決を受けた。その後この所長は釈放されて僧侶となり、戦没者・刑死者の冥福を祈りながら余生を過ごしたという。
なお、爆撃中に撃墜されて落下傘で地上に降りた米兵の例は日本各地に生じているが、中にはその場で簡易軍事裁判が行われ、銃殺、あるいは斬殺した例は少なくない。場合によっては住民がめった打ちにして殺した例もあった。しかし米軍はB29が墜落した場所を正確に把握していて、終戦後直ちに日本の各地に捜索に走り、聞き取りをしながら徹底的に調査した。その結果、処刑に関わった元将兵は逮捕され、上記のBC級戦犯として横浜軍事法廷で裁かれ、その主犯格の多くが死刑となっている。
戦後の出来事
街の復興
昭和20年(1945)8月15日の終戦を受け、人々は空襲の恐怖から解放され、一面焼け野原と化した街の瓦礫の片付けを始め、バラック建ての家も日に日に増えていった。しかし極度のインフレと物不足から、人々は空いている土地を見つけて家庭菜園を作り飢えをしのぐ日々を送った。このような家庭菜園は2年後にはほぼ全区に散在し、組合が結成されるほどとなった。
新宿や池袋と同様、渋谷駅周辺のヤミ市は急速に膨れて活況を呈したが、連合国軍の指示により駅周辺の露天商は閉鎖を迫られた。それでも昭和24年には区内の商店数は3523店となり、翌25年11月には商店連合会が結成され、街は順調に発展し、32年(1957)、日本初の渋谷駅前地下商店街も完成した。なお、渋谷駅前の忠犬ハチ公像は、戦時下の19年、金属類回収令によって供出されたが、23年に再建された。
占領軍による用地接収と東京オリンピック
終戦直後の9月から占領進駐軍による土地建物の接収が日本の各地で始まった。渋谷は旧帝国陸軍の広大な代々木練兵場が接収され、米空軍とその家族のための団地、ワシントンハイツとなり、恵比寿の海軍技術研究所跡は連合豪州軍のエビスキャンプ(目黒区参照)となった。
ちなみに代々木練兵場は、明治42年に現在の代々木公園一帯からNHK放送センターや渋谷区役所、代々木競技場にかけての広大な土地に、当時の陸軍省の軍事練習場として整備された。その翌明治43年12月に、フランスからの複葉航空機とドイツから単葉機を陸軍が持ち帰り、代々木練兵場で二機による初の試験飛行が行われた。これは高度は50−70mで数分間の飛行であった。なお日本人設計の複葉機も試されたが馬力不足で失敗した。ここは昭和初期まで試験飛行場として使われた。現在も地下鉄代々木公園駅近くの公園一角に「日本航空発始之地」の碑がある。
ワシントンハイツは米軍の要求によって日本政府の責任と負担に基づいて建設された。代々木の広大な敷地には兵舎のほか827戸の住宅、さらに学校、教会、劇場、商店、将校クラブなどが設けられ、近代的なアメリカの町並みが出来上がっていたが、周囲は塀で囲われ、日本人は立入禁止であった。
昭和27年5月1日に、大学生らを中心とする反米デモが起こり「Yankee, go home !」の掛け声のもと、都心ではアメリカ車が焼き討ちにあうなどした。ワシントンハイツ内ではマシンガンで武装するなどの対応がとられたが、警視庁による周辺警備もあり無事であった。その後の7月に日米安保条約に基づく無期限使用施設の指定を受け、治外法権的場所として東京都心に存在した。
しかし間もなく東京オリンピックが昭和39年(1964)に正式に開催されることになり、そこでワシントンハイツを競技場用地と選手村として利用することが36年に決定、交渉の結果全面返還されることとなった。代替施設として調布飛行場周辺を提供、移転費用の全額を日本が負担した。
そして国立代々木競技場が建設され、旧ハイツの戸建住宅は選手村として改修、敷地総面積は66万平方mに及び、5900人を収容する施設となった。現在は代々木公園として都民の憩いの場となっている。その側に建設された国際放送センターは、NHK放送センターとなった。